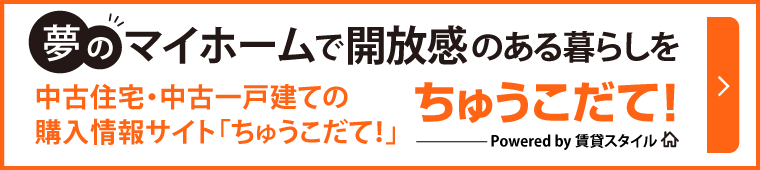The post 畳のメンテナンスの値段は?失敗しない選び方や依頼の方法を解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>畳が古くなっているというのは見た目でわかっても、メンテナンス作業の種類や値段、タイミングなどはよくわからないものです。
この記事では、畳のメンテナンスの値段や失敗しない選び方、依頼の方法などを解説します。
畳とはどんなものかからご説明しますので、畳のメンテナンスを検討中の方はぜひ参考にしてください。
\ 理想の中古物件を探したい /
畳の機能と種類
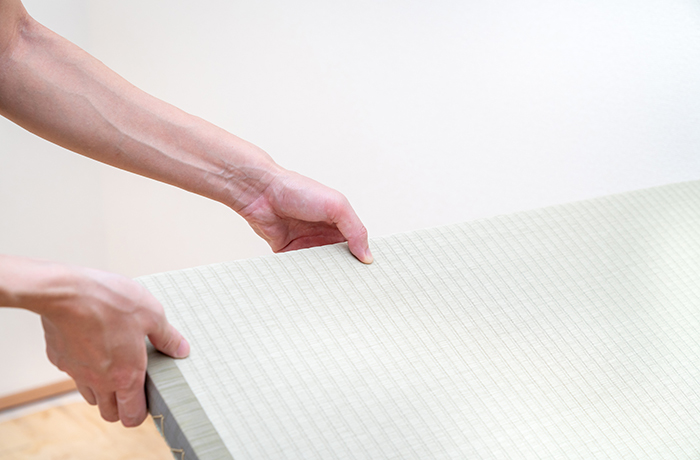
畳の機能や種類の説明を通して、畳のメンテナンスをする意味をご紹介します。
畳の機能
畳が古くから生活様式の変わった現在まで愛用されてきた理由は、クッション性や防音性、空気の清浄化、調湿や芳香の癒やし効果などがあるためといわれています。
畳の和室は減少傾向にありますが、以下のアンケートのように「畳の和室が欲しい」という方は約7割にのぼります。
| あなたは理想の家に住めるとしたら、和室、畳のある部屋が欲しいですか? | 欲しい:38.4% |
| やや欲しい:30.7% | |
| あまり欲しくない:19.5% | |
| 欲しくない:11.5% |
2022年 プラネット調べ
和室はシンプルな生活様式によく合い、掃除や手入れもしやすく機能的ですが、いつまでも性能が変わらないわけではありません。
新しい畳にすると気持ちがいいですが、い草のにおいが広がり、クッション性のある踏み心地が戻ることなどが作用しているでしょう。
新しい畳のにおいには心を癒やす効果があります。い草の芳香成分は森林浴効果と同じ癒やし成分が含まれています。
また、高いリラックス効果のある成分も含まれています。
表面が硬くなってくると防音、防湿効果も劣ってくるので、専門的なメンテナンスを依頼しましょう。
畳の種類
現在畳のサイズはおもに以下の4種類あります。
畳の種類
| 京間(本間・関西間) | 縦95.5cm×横191cm | 室町時代の貴族の間で、最初に普及したサイズ。板の間に代わってベッドやクッションの機能を担った。
中部地方以西に多い。 |
|---|---|---|
| 中京間(三六間) | 縦91cm×横182cm | 西日本で庶民の間に普及した。
京間=貴族と同じ大きさの畳を遠慮して京間より少し小さい(9割程度) |
| 江戸間(五八間・関東間) | 縦87cm×横176cm | 関東で一般庶民に使われるようになった結果、住宅事情に合わせて京間より8割程度の大きさに。
関東以北で多いサイズ。 |
| 団地間(五六間) | 最大縦81cm×横170cmまで各種 | 高度経済成長期に集合住宅用にできたサイズ。
江戸間より小さいサイズで、京間と比べると8割弱程度の大きさのものを指す。 全国で普及。 |
このほかに、近年では和モダンの志向に合わせて正方形で縁なしの琉球畳や、カラフルな和紙畳などがあります。
和紙畳や樹脂製畳は撥水加工がされていて感触がさっぱりしており、直接日光に当たっても色褪せしにくく、高い耐久性を持つため、子育てにも向いている畳です。
琉球畳は近年カジュアルさやおしゃれさから普及が進んできています。
置き畳としてとても雰囲気が良いのが特徴です。
琉球畳のデメリットは、一般的な畳とは異なり畳縁がないため、耐久性が低くなりやすく、置き畳でも枠を作ったほうが長持ちします。
七島い草など高級品を使って和室を新調すると、6畳で20万円以上と、かなり高価になる傾向があります。
畳の構造

メンテナンスの方法をわかりやすくするために、畳の構造をご説明します。
畳は大きく分けて以下の3つで構成されます。
- 畳表(たたみおもて):畳の表面に張られたゴザ
- 畳縁(たたみべり):畳の側面の生地
- 畳床(たたみどこ):畳の本体部分
畳表(たたみおもて)
畳表は、平行に張られた経糸(たていと)に対し、い草を緯糸(よこいと)として交互に織り込んで作ったゴザです。
畳の表面を覆うために使用し、い草以外の材質を使うこともあります。
畳表は、織り込むい草の本数が多いほど質が良く、経糸の素材には綿よりも麻が採用された畳表のほうが高級です。
また、い草の生育状態や加工の仕方が均一なものが、耐久性も仕上がりの美しさも良いです。
風合いよりも耐久性を重視して和紙やパルプ、化学繊維でい草風に仕上げた畳表も作られています。
畳縁(たたみべり)
畳縁は畳の側面に縫い付けてある生地で、畳表の補強や畳同士の隙間を埋める役割をしています。
畳のアクセントや部屋の装飾としてもとらえられ、なかなか目にしない奇抜なものを含め、豊富なデザインが準備されています。
綿や麻の糸を使った昔ながらの畳縁のほか、安価で丈夫な化学繊維製の畳縁も普及中です。
畳縁は畳店で扱うものが数百種類あり、材質も綿100%・綿50%+ナイロン50%・ナイロン100%などさまざまです。
昔からある純綿の無地は座敷・客間などでよく使われますが、最近ではナイロン地のカラフルな無地や柄ものも人気が高まっています。
綿100%の無地は落ち着きと高級感がありますが、高価なものが多く、日焼けにより変色しやすいのが短所です。
ナイロン地のものは変色しにくく耐久性が高いのですが、熱に弱いという短所があります。
和室の雰囲気を変えてリフレッシュしたい場合、畳縁選びは重要なポイントでしょう。
畳床(たたみどこ)
畳床はおもに稲藁(いなわら)を何層にも重ねて圧縮して縫った藁(わら)床が使用され、使われている稲藁の品質によって等級が分かれます。
畳表を張る芯として使用され、畳の弾力や吸湿性ほかの機能を左右します。
畳床の素材の種類は外見では判断できませんが、藁のほか発泡スチロールまでさまざまです。
畳床の材質
| 稲藁 | 稲藁(いなわら)を何層にも重ねて圧縮して縫い上げたもの。
稲藁の品質に応じて等級分けされ、一般的な住宅には二級品が広く普及している。 |
|---|---|
| 建材床 | ポリスチレンフォームなどが主材料。
畳が軽量化できる。稲藁の流通量の減少で普及した。 |
| 藁サンド床 | 木質繊維を圧縮したインシュレンボードを、藁と藁の間に挟んで使用する。
ポリスチレンフォームを藁でサンドイッチするタイプもある。 |
畳のメンテナンスはどんなときに必要か

畳のメンテナンスの時期は、どのように判断したら良いのでしょうか。
最終的には専門業者の確認が確実ですが、目安として知っておきましょう。
畳の状態から判断する
畳表の色褪せや擦り切れ、畳の弾力、虫、カビ(見た目やにおい)などの状態を確認してみましょう。
畳表を張り替えてから年数が過ぎていたり、畳表をこすった際に、い草が服につくようになってきたように感じたりすることはないでしょうか。
畳の芯材である畳床の経年変化で、踏むとギシギシときしみ音が出たり、ブカブカと浮き上がるような感触が出たりしていないかもポイントです。
ブカブカと浮くような感触になってきたときは、畳の内部が劣化してきている証拠です。
その場合は、畳を畳床ごと新調する時期にきています。
経過年数
経過年数の目安は、基本的に新調から2年から5年で裏返し、裏返しから約5年で表替え、前回の新調から10~15年で新調をおこないます。
| 裏返し | 約2~5年 |
|---|---|
| 表替え | 約4~7年 (裏返しをおこなってから約5年) |
| 新調 | 約10~15年 |
ただし畳の置かれた状況によっては、耐用年数よりも早く傷みが出ることもあるので、畳の状態を見て業者にチェックを依頼するのが良い場合もあります。
例えば締め切った和室など、畳にカビやダニが発生していたり、湿度が高く傷みが早かったりする場合など、年数より早く傷んでしまうこともあるでしょう。
中古一戸建ての畳は修繕歴がわからないことも
中古物件の建物の状態をもっとも細かく知る手段として、売買契約の際に重要事項説明書と一緒に交付される、「物件状況等報告書」があります。
この物件状況等説明書か、買い主募集のための販売図面に畳を含めたリフォームやメンテナンスの履歴が記載されている場合がありますが、内装の細かい管理の記載は義務ではありません。
できるようであれば、売り主に畳のメンテナンスの状況を確認しておくのが良いでしょう。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 理想の中古物件を探したい /
畳のメンテナンスの方法と値段

畳のメンテナンス方法の基本は表替え・裏返し・新調の3種類です。
このどれをおこなうかは、業者の所見をもとに、依頼する方が判断します。
畳を裏返す
既存の畳表を裏返して再利用する方法です。
畳床に固定している糸をはずす作業もともなうため、側面の畳縁は新しいものへ交換することになります。
値段の相場は1畳あたり約4,000円で、畳縁の値段などで価格は上下します。
作業期間は1日で済むことが多いでしょう。
畳の表替えをする
畳表と畳縁を新調する方法で、畳床は既存のものをそのまま利用し、新品のような見た目になります。
4~8年くらい経った畳や、一度裏返しをおこなってから5年ほど経過した畳に適しています。
い草のささくれ、畳が光沢を失うなどの状態も、表替えの施工の目安です。
値段の相場は1畳につき5,000~2万円前後で、畳表のグレードによって大きく変わります。
一戸建て用はマンション用に比べて、少し割高となります。
表替えも大体1日で終了することが多いようです。
畳を新調する
畳を敷いてから10~15年くらい経った頃が、畳を新調するタイミングです。
畳のへこみ、ダニが気になるなどのほか、畳を変えることで部屋の雰囲気を変えたいときなどもおすすめです。
新調の値段の相場は1畳につき1~3万5,000円程度が主流でしょう。
畳表・畳床・畳縁のグレードによって価格は大きく異なり、高級品はこれよりさらに高額となります。
新調する場合、既存の畳を業者が採寸をおこない後日、新しい畳が完成してから入れ替え作業をします。
裏返しや表替えのように、「作業中は畳がない」という状態にはなりませんが、施工にかかる日数は、採寸から入れ替えまで2~10日くらいです。
料金は、例えば畳のサイズが同じ江戸間でも、畳の厚みによって変わることがあります。
平均的な畳の厚みは地域差があり、中部~関西は55mm、関東は60mmくらいで、大体30mm以上の厚みがあることが多いですが、最近では13~15mmの薄い畳があります。
薄い畳は製造に特殊な技術を要するため、業者によっては厚みが25mm以下の場合、通常価格の2割増しくらいになることもあるでしょう。
良い畳の特徴とは
良い畳とはどのようなもので、お金をかける意味はどのようなところにあるのでしょうか。
良いい草を選別して作られた高級の畳表は色や太さ、光沢が均一で表面がきれいです。
茎がしっかり太くて切れにくいために、表面が長くきれいな状態に保てます。
また、畳表の1畳あたりのい草の使用量が多いと、弾力も良くなります。
畳床の違いは、どちらかというとお部屋の使用頻度、床下の状態、段差などの具合に合わせて用途に合ったものを選ぶのが良いでしょう。
建材床は木質ボードの使用でダニなどの発生が少なく、価格も安価に抑えやすいですが、新調直後は稲藁の床に比べて、やや硬めに感じることもあります。
稲藁を使用した畳床は足触りが良く耐久性・吸湿性に優れているのが特徴です。
稲藁床や稲藁のサンドイッチ床は、防虫シートでダニの発生を抑えます。
畳はDIYでメンテナンスできるか

畳のメンテナンスをDIYでおこなう話はあまり聞きませんが、DIYでできることはあるのでしょうか。
畳の張り替えはプロに依頼を
畳の状態の判断や専用の道具や機械、熟練の技術を必要とする畳のメンテナンスは、アマチュアがDIYでおこなうメリットは少ないでしょう。
畳のメンテナンスの頻度を考えると、道具をそろえたり技術を覚えたりすることは割に合わないといえます。
また、作業が上手くいかなかった場合に、畳をダメにする可能性も高い点も、DIYがしにくい理由です。
DIYでもできるおしゃれな置き畳
琉球畳などを使った「置き畳」なら、畳の厚さや敷き詰めるサイズを合わせられれば、DIYできる可能性があります。
畳の厚みは稲藁床の畳の55~60mmが標準でした。
しかし近年住宅のバリアフリー対応や床暖房などの内装の多様化で15~30mmの畳が多くなっています。
30mm以下の畳を薄畳と呼び、置き畳の多くはこの30mmほどで作られてます。
置き畳はフローリングなどの上でも可能です。フローリングとの段差や、敷居戸の隙間を埋める調整材も販売されているので、トライするのも良いでしょう。
広めのリビングのなかに置き畳を使った小上がりスペースを設けると、さまざまな用途のユーティリティスペースとなります。
例えば小さな子どもの寝かしつけや遊びの見守り、気軽に寝そべったり、来客の就寝スペースにできたりするなどです。
失敗しない畳のメンテナンスの依頼方法

この項では、畳のメンテナンスを業者に依頼するうえでの注意点をまとめました。
メンテナンスを依頼する業者の種類
畳のメンテナンスは、ほぼ畳専門店かホームセンターへの依頼となります。
それぞれの特徴をご説明します。
畳専門店
専門知識や資材の豊富な畳専門店は、地元業者なら依頼する安心感は抜群な反面、最初は少し敷居が高く感じるかもしれません。
畳専門店のメリットとデメリットは以下です。
| 畳専門店に依頼するメリット | ・扱う工法や素材の種類が豊富 ・事前のチェックで的確なアドバイスを受けやすい ・アフターフォローも依頼しやすい |
|---|---|
| 畳専門店に依頼するデメリット | ・営業などの窓口がないことが多い ・職人さんとじかで話しづらい ・施工場所の家から遠い場合もある |
ホームセンター
ホームセンターは気軽に依頼がしやすい反面、作業する方と事前にコミュニケーションが取りづらい面があります。
ホームセンターのメリットとデメリットは以下です。
| ホームセンターに依頼するメリット | ・馴染み、最寄りの店で畳の張り替えが依頼できる ・大量仕入れで値段が割安なこともある ・価格がわかりやすい |
|---|---|
| ホームセンターに依頼するデメリット | ・安い畳の耐久性や仕上がりがもう一つの場合も ・オプションの追加で値段が高くなる場合がある ・下請けが多く作業者に事前に要望を伝えづらい ・口コミが少なく、判断材料が少ない |
業者選びの基準
とくに畳店の場合、良い業者を選ぶ基準は以下を参考にしてください。
- たしかに地域密着の業者かを確認する。Webでエリア名で調べて依頼したら、実は遠方の業者だったケースも多い。
- 契約を急がせないか。顧客の都合を考えない強引な勧誘がある場合は、注意が必要。
- 財団法人日本規格協会と全日本畳事業組合主催の、品質管理責任者資格があるか。
これらを満たしたうえで、見積もりの細かさや透明性、質問への回答が的確か、無理に高額の商品をすすめないかなどの点を確認しましょう。
見積もりは、ホームページに掲載されているものと極端に値段の違いがないかを見ましょう。
値段の違いがあれば、その根拠をわかりやすく説明してもらえるかも大切です。
また、相見積もりを取り、対応や価格を比較することもおすすめします。
畳の張り替えの値段を抑えるコツ
畳の張り替えの値段を抑えるのは、やはり見積もり段階での工夫が大切です。
Webサイト上で価格を見比べ、相見積もりをしっかり取ることで価格の違いがわかり、言い値になることを回避できるでしょう。
また、値段だけではなく価格に見合った商品や仕事のクオリティも、口コミなどでチェックして、同程度の内容で安い業者を探すこともできます。
ホームセンターを利用する場合は、普及品は大量発注の分、畳専門店の同じ質のものより安い可能性があるので、高級畳を望まなければ検討の価値があります。
そして作業以外の工賃は、家具を動かすことや畳の処分など、可能であれば自分でやるようにすれば、値引きの可能性があるので問い合わせをしてみましょう。
畳のお手入れで寿命を延ばす
畳の正しい手入れをすることで、畳のメンテナンスの時期を延ばせるかもしれません。
また、メンテナンス後の畳を長く良い状態に保つために、以下のお手入れを定期的におこなうことをおすすめします。
まず、畳の状態が良くないときの対処方法は以下です。
| カビの発生 | 用意するもの:アルコール除菌スプレー・雑巾・歯ブラシ・塩素系漂白剤
アルコール除菌スプレーを雑巾にたっぷり含ませる。カビの場所に直接吹き付けるとスプレーの勢いでカビの胞子が拡散するので注意。 カビが生えている部分に、雑巾にカビを移していく要領で押し当てる。カビを広げないよう、まめに雑巾の面を変える。 時間が経ったカビは、奥まで入り込んで黒ずんだシミになっている。シミは液体状の塩素系漂白剤を、200倍以上に水で薄めて使う。 塩素系漂白剤をそのまま使うと、畳の色素が抜けて傷むため、しっかり薄める。 雑巾などに染み込ませてカビの部分だけを拭き、最後に水拭きをして漂白剤を残さず拭き取り、乾燥させる。 窓やドアを開けて換気し、乾燥させる。使った雑巾はそのまま処分する。 |
|---|---|
| ダニの発生 | ダニは乾燥と高温に弱いので、天日干しもしくは布団乾燥機などで60℃以上の熱風により駆除する。
天日干しは、ドライバーなどを使って畳を上げ、日当たりの良い場所で日光に当てる。その間、普段取れない畳の下のホコリを掃除機で吸い取る。 あるいは畳の上に直接布団乾燥機を置き、その上から掛け布団などをかけて乾燥させる。 |
| 液体をこぼした | ジュースなど飲みものをこぼしたときは、時間を置かずすぐに乾いた布やシートで水気を拭く。
そのあとで固く絞った濡れタオルで表面の汚れを拭き取る。 時間が経つと畳が水分を吸収してシミになるため、即座に対応することが大切。 |
| 畳表のささくれ | 用意するもの:木工ボンド・筆・雑巾
まず後述の普段の方法で畳を掃除してホコリやチリを取り除く。 乾拭きのあとに、立ったい草を畳の目に沿い、しっかりとなじませるように寝かせる。 ささくれが落ち着いたら、薄めた木工ボンドを筆で塗り、十分に乾燥させる。 畳の傷が広がる前におこなうと、ある程度きれいに保てる。 |
また、普段の畳のお手入れの基本は以下のようにおこなってください。
| 1.掃除機やほうきでゴミやホコリを掃除 | ほうきを畳の目に沿ってはき、ゴミやホコリを取り除く。
掃除機を使用するときは先端のブラシの回転を止めて、畳の目に沿い強く押し付けないようにゆっくり吸い取る。 掃除機は、畳1畳に対して1分程度は時間をかけて吸引するのが良い。 |
|---|---|
| 2.隙間に詰まったゴミやホコリをほうきで取り除く | 畳の縁などの隙間のホコリや髪の毛などのゴミは、ほうきで掻き出して掃除機で吸うか、乾いた布で集める。
細かなゴミを掻き出すときは、小さいほうきや柔らかめのブラシが便利。 |
| 3.雑巾で水拭きする | 畳は湿気を嫌うのであまり水を使わないのが基本。
しかし月に1回程度は固く絞った濡れ雑巾で丁寧に畳の表面の汚れを拭き掃除する。必ず畳の目に沿うようにおこなう。 |
| 4.乾拭きで水分を拭き取る | 最後に乾拭きで仕上げ。雑巾は変色などのリスク防止のため、化学繊維ではなく昔ながらの柔らかい綿などの雑巾を使用する。
米ぬかを包んだ不織布で畳の表面を軽くこすっておくと、米ぬかの油分で防水と艶出しができる。 |
まとめ

畳のメンテナンスの値段や失敗しない選び方、依頼の方法などを解説しました。
住環境研究所の2016年の調査データによると、和室のニーズは高齢の方より子育て世帯のほうが高いことがわかっています。
同調査では20代76.0%、30代75.2%、40代70.6%と、畳が生活のなかで必要とされていることがわかります。
同じ和室でも使用頻度によって畳のグレードを変えるなど、長く過ごす部屋では良いものを使うという考え方も、値段検討の一つの基準としておすすめです。
ちゅうこだて!では、多数の中古物件を取扱っております。
ぜひご覧になり、理想の住宅をお探しください。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 理想の中古物件を探したい /
The post 畳のメンテナンスの値段は?失敗しない選び方や依頼の方法を解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>The post 建ぺい率とは何?計算方法や容積率との違いをわかりやすく解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>建ぺい率とはその土地に建てられる建物の規模を決めるルールです。
どれだけ広い土地を購入しても、建ぺい率の上限次第では小さい建物しか建てられない可能性があります。
この記事では建ぺい率とはどのようなルールなのか解説します。
計算方法や緩和条件、容積率との違いなどもまとめました。
\ 理想の中古物件を探したい /
建ぺい率とは

建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合です。
敷地面積は建物を建てる土地の面積、建築面積は建物を真上から見た面積を指します。
簡単にいえば、真上から見たときに建物が土地の何割を占めているかを表しています。
数値が大きいほど土地いっぱいに建物を建てられるイメージです。
逆に数値が小さいほど土地に余白をつくらなければならず、建てられる建物の規模が小さくなります。
土地ごとに上限が決まっているため、同じ面積の土地でも建てられる建物の面積は異なります。
建ぺい率の意味・目的
建ぺい率は、防火対策、通風と日当たり、景観の美しさを保つ目的で制限されています。
一つ目の目的は、防火対策として都市部などで建物が密集するのを防ぐことです。
建物が密集している地域で地震や火災が起きると、延焼が起きやすいうえに避難経路を確保できない恐れがあります。
建物同士がある程度離れていれば、災害時の安全性を確保できます。
二つ目は建物の間に隙間をつくり、通風と日当たりを確保する目的です。
すべての建物が敷地いっぱいに建っていると、奥のほうまで風や光が行きわたらず劣悪な環境になってしまいます。
規制を設けることで、どの場所でも平等に快適な環境をつくれる仕組みです。
三点目は景観の美しさを保つ目的です。
圧迫感のある街並みになることを防ぎつつ、地域全体で統一感を持たせて美しい街並みを形成できます。
建ぺい率の計算方法
建ぺい率は以下の計算式で求められます。
建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100
具体的な事例をもとに、計算してみましょう。
敷地面積100㎡の土地で、建築面積が50㎡の建物を建てたケースと80㎡の建物を建てたケースの建ぺい率を計算します。
まずは敷地面積100㎡の土地で建築面積50㎡の建物を建てたケースです。
50㎡(建築面積)÷100㎡(敷地面積)×100=50%
次に敷地面積100㎡の土地で建築面積80㎡の建物を建てたケースです。
80㎡(建築面積)÷100㎡(敷地面積)×100=80%
このように敷地面積と建築面積がわかれば自分で簡単に計算できます。
建築面積に算入される部分
建ぺい率を計算する場合に覚えておきたいのが、建築面積に算入される部分と算入されない部分があることです。
建築面積は建物を真上から見下ろしたときの水平投影面積です。
1階と2階で面積が異なる場合は、上から見て広いほうの面積が採用されます。
建物を真上から見たときに柱・壁・屋根が覆い隠す範囲をイメージするとわかりやすいでしょう。
これだけであれば考え方はシンプルですが、次に説明する建築面積に算入されない部分は差し引いて計算しなければなりません。
建築面積に算入されない部分
建築面積を計算するときは、以下の部分を建築面積に算入しないルールがあります。
- 外壁からの突出が1m未満の軒・庇
- 地下室があり、地盤面から1m以下の高さにある部分
- 高い開放性を有する構造
軒や庇が突き出している場合、外壁からの突き出しが1m未満であれば、建築面積に算入されません。
1m以上突き出している場合は、先端から1m後退した範囲のみを建築面積に算入します。
地盤面から1m以下の高さにある地下室も建築面積に算入しません。
大きな地下室をつくっていても、高さの条件を満たしていれば建築面積から除外します。
一定の条件を満たす高い開放性を有する構造は、先端から1mの部分を建築面積から不算入にできます。
例えばポーチやカーポートの一部が該当する可能性があるでしょう。
不算入になるための条件は以下のとおりです。
- 外壁のない部分が連続して4m以上
- 柱の間隔が2m以上
- 天井の高さが2.1m以上
- 地階を除く階数は1であること
建ぺい率と容積率の違い

敷地面積に対してどのくらいの規模の建物を建てられるか決める指標となるのが容積率です。
容積率とは敷地面積に対する延床面積の割合です。
建ぺい率は建築面積の割合を計算するのに対して、容積率は延床面積の割合を計算する点が大きく異なります。
延床面積とは建物におけるすべてのフロアの床面積を合計したものです。
容積率は3次元的な空間の制限で、容積率が大きいほど建物の規模も大きくなります。
容積率の意味・目的
容積率を定めている目的は、人口過密や高い建物の乱立を防ぐためです。
防火対策、風通し・日当たりの確保、景観の美しさを保つことも容積率の目的として含まれます。
容積率の制限がなければ、どこでも高層ビルを自由に建てることができ、多くの人々が住めることになります。
過密状態になった都市は、住みやすい環境とはいえません。
電力や上下水道など生活に欠かせないインフラがパンクしてしまい、交通渋滞を起こすなど生活にさまざまな弊害が起こります。
このように都市の住みやすさが損なわれないよう、容積率で人口過密を防いでいるのです。
容積率の計算方法
容積率は以下の計算式で求められます。
容積率(%)=延床面積÷敷地面積×100
例えば敷地面積100㎡の土地で延床面積が200㎡の建物を建てた場合の計算式は、以下のとおりです。
200㎡(延床面積)÷100㎡(敷地面積)×100=200%
敷地面積100㎡の土地で延床面積が400㎡の建物を建てた場合の計算式は、以下のとおりです。
400㎡(延床面積)÷100㎡(敷地面積)×100=400%
このように敷地面積と延床面積がわかれば自分で簡単に計算できます。
用途地域と建ぺい率・容積率の関係

建ぺい率と容積率は用途地域ごとに上限が設けられています。
用途地域とは計画的な市街地形成のため、用途に応じて分けられた13種類の地域です。
住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類によって構成されています。
用途地域を定めることで建物が無秩序に混在することを防ぎ、合理的な街づくりができます。
建物を建てる際は敷地がどの用途地域にあるか確認することが大切です。
そのうえでそれぞれの上限を考慮し、建物の規模を決めます。
ただし容積率に関しては前面道路の幅が狭い場合、用途地域による制限よりもさらに厳しい制限がかかる可能性があるため注意しましょう。
用途地域ごとの建ぺい率・容積率の上限
13種類の用途地域は以下のとおり、建ぺい率と容積率が決まっています。
| 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 30・40・50・60 | 50・60・80・100・150・200 |
| 第二種低層住居専用地域 | 30・40・50・60 | 50・60・80・100・150・200 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 30・40・50・60 | 100・150・200・300・400・500 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 30・40・50・60 | 100・150・200・300・400・500 |
| 第一種住居地域 | 50・60・80 | 100・150・200・300・400・500 |
| 第二種住居地域 | 50・60・80 | 100・150・200・300・400・500 |
| 準住居地域 | 50・60・80 | 100・150・200・300・400・500 |
| 田園住居地域 | 30・40・50・60 | 50・60・80・100・150・200 |
| 近隣商業地域 | 60・80 | 100・150・200・300・400・500 |
| 商業地域 | 80 | 200・300・400・500・600・700・800・900・1000・1100・1200・1300 |
| 準工業地域 | 50・60・80 | 100・150・200・300・400・500 |
| 工業地域 | 50・60 | 100・150・200・300・400 |
| 工業専用地域 | 30・40・50・60< | 100・150・200・300・400 |
建ぺい率・容積率の上限の調べ方
土地の用途地域によって建ぺい率と容積率の上限の範囲がわかりますが、具体的にどのような組み合わせになるかは土地ごとに調べる必要があります。
確実な方法は、土地の住所を管轄する市町村の建築指導課や都市計画課などに問い合わせることです。
市町村によっては、ホームページ上で色分けした地図を公開している場合もあります。
売り出し中の土地の建ぺい率・容積率を知りたい場合は、物件情報に記載されている場合もあるでしょう。
物件情報に記載がない場合は販売主の不動産会社に問い合わせれば教えてもらえます。
2以上の用途地域にまたがる場合の建ぺい率
建ぺい率の上限を調べていると、土地が2以上の異なる用途地域にまたがっている場合があります。
その場合は用途地域別の敷地面積の割合によって、それぞれの数値を按分計算しなければなりません。
建ぺい率60%と80%の用途地域にまたがる100㎡の土地を想定して、計算してみましょう。
60%の部分の面積が30㎡、80%の部分の面積が70㎡とすると、計算式は以下のとおりです。
(30㎡×60%+70㎡×80%)÷(30㎡+70㎡)=0.74(74%)
建ぺい率は74%となるため、建築できる建築面積は100㎡×74%=74㎡が上限になります。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 理想の中古物件を探したい /
建ぺい率の上限が緩和される条件

一定の条件を満たす土地では、建ぺい率の緩和規定が適用されます。
条件に応じて建ぺい率の上限が上乗せされるため、建築面積を増やしたい方はぜひチェックしておきましょう。
建ぺい率の上限が緩和される条件は以下のとおりです。
- 防火地域・準防火地域の耐火建造物
- 特定行政庁が指定した角地
- 省エネ化をおこなう建築物
防火地域・準防火地域の耐火建造物
防火地域に耐火建築物を建てた場合と、準防火地域に耐火建築物および準耐火建築物を建てた場合、建ぺい率の上限が10%上乗せされます。
防火地域や準防火地域は火災の被害を抑えたり緊急車両の通行を妨げないようにしたりする目的で、指定されている地域です。
多くの場合、駅前など多くの建物が密集している場所や幹線道路沿いなどが指定されています。
耐火建築物は主要構造部(柱、梁、床など)や開口部の耐火性能を高めた建物です。鉄筋コンクリート造や鉄骨モルタル造などが該当し、戸建て住宅よりもマンションや商業施設といった大規模建築物で採用されています。
準耐火建築物は耐火建築物に準じた耐火性能を持つ建築物です。
特定行政庁が指定した角地
特定行政庁が指定した角地にある建物は、建ぺい率の上限が10%上乗せされます。2方向以上が道路に面している角地は、防火対策や通風・日当たりが確保しやすいためです。
角地の建ぺい率が緩和される条件は、特定行政庁によって異なります。
例えば東京都における条件は、敷地の周辺の3分の1以上道路または公園等に接している、かつ1~3のいずれかに該当することです。
- 二つの道路が隅角120度未満で交わる角敷地
- 幅員がそれぞれ8m以上の道路の間にある敷地で道路境界線相互の間隔が35mを超えないもの
- 公園等に接する敷地またはその前面道路の反対側に公園等がある敷地で前記1および2に掲げる敷地に準ずるもの
省エネ化をおこなう建築物
国土交通省は省エネ改修や再生可能エネルギー設備を設置する場合、建ぺい率などの規定を特例許可制度で緩和する予定です。
省エネ性能を高めるための日射を遮る庇の設置、断熱性能を高めるための外壁工事、太陽光発電設備などの設置工事を実施する建築物が対象になります。
建ぺい率ぎりぎりで建てられている住宅は、省エネ改修をおこなうと上限をオーバーしてしまう可能性があります。
このような場合に、構造上やむを得ないことを条件として建ぺい率の制限を緩和し省エネ改修をおこなえるようにするものです。
具体的な緩和内容は特定行政庁によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
建ぺい率・容積率以外の建築制限

建ぺい率や容積率以外にも建築制限はあります。
戸建て住宅を建築、取得する際は、以下の建築制限を押さえておきましょう。
- 斜線制限
- 日影規制
- 絶対高さ制限
- 高度地区の制限
斜線制限
斜線制限は建物の高さを規制するための建築制限です。
ある地点から建物に向かって斜線を引き、その範囲内に建物が収まるようにしなければなりません。
斜線制限には道路斜線・北側斜線・隣地斜線の3種類があります。
道路斜線制限は道路の通風・採光を確保する目的で、前面道路幅に対して1.25倍または1.5倍以下の傾斜勾配まで高さを規制するものです。
北側斜線制限は北側の隣地の通風と採光を確保するために、建物を北側の隣地境界線から少し離して建てて、北側に向かって建物の高さを低くする必要があります。
隣地斜線制限は高さ20mを超える建物が対象になるため、戸建て住宅が影響を受けることは少ないでしょう。
日影規制
日影規制は冬至の日に一定時間以上の日影ができないよう、建物の高さを規制する建築制限です。
周辺敷地の日照を確保して、住みやすさが損なわれないようにすることが日影規制の大きな目的です。
日影規制は商業地域、工業地域、工業専用地域以外の用途地域で定められています。
敷地境界線から5〜10mの範囲と10m超の範囲に分けて、それぞれ日影時間と測定水平面が規制されます。
例えば「5h-3h/4m」と表記されている場合は、5〜10mの範囲は5時間、10m超の範囲は3時間まで、地盤面から4mの高さが日影になっても良いという意味です。
2階建ての場合はほとんど日影規制の影響を受けませんが、3階建て以上の場合や2階建てでも天井高を高く設定している場合は注意が必要です。
日影規制によって建物の高さやプランが制限される場合があるため、あらかじめ調べておきましょう。
絶対高さ制限
絶対高さ制限は建物の高さを制限するものです。
都市計画によって10mまたは12mのいずれかが設定されていて、この高さを超えることはできません。
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域で適用されます。
これらの用途地域では絶対高さ制限が設けられている代わりに、隣地斜線制限がないのが特徴です。
建物の高さは容積率によっても制限されますが、絶対高さ制限は容積率よりも優先順位が高い制限となっています。
たとえ容積率の上限内に収まっていても、絶対高さ制限を超えている建物は建てられません。
高度地区の制限
都市計画法の高度地区の制限によって、建物の高さに制限がかかることもあります。
高度地区は2種類あり、建築物の最低限度の高さを定める最低限度高度地区と最高限度の高さを定める最高限度高度地区のいずれかです。
最低限度高度地区はおもに商業地やオフィス街で規制されることが多く、住宅地ではあまり関係ありません。
住宅を建てる際に注意しておきたいのは、最高限度高度地区です。
高度地区の内容は自治体ごとに異なり、多くの自治体では高さ制限と北側斜線制限の両方がかけられています。
詳しくは自治体のホームページや窓口に問い合わせる方法などで確認しましょう。
建築制限に違反するとどうなる?

建ぺい率をはじめとした建築制限に違反した建物は違反建築物として扱われ、多くの弊害が発生します。
新築時だけでなく、リフォームを検討するときにも建築制限の遵守が不可欠です。
違反建築物になる
違反建築物とは建築当初から法令に適合していない建築物のことです。
例えば、建築確認申請後、無許可で計画変更をおこない法令に適合しなくなった建築物は違反建築物として扱われます。
違反建築物であることが判明した場合は、特定行政庁から是正命令が下るため要注意です。
施工の停止を命じられるか、または建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替え、使用禁止、使用制限など厳しい措置がとられます。
違反建築物と混同しやすい言葉として、既存不適格建築物があります。既存不適格建築物とは建物が建築された時点では合法だったものの、法令の改正などによって法律の規定を満たさなくなった建築物です。
既存不適格建築物はそのまま利用し続けても問題はありませんが、保安上の危険や衛生上有害である場合は建築物の除去修繕や使用制限などを求められる可能性があります。
住宅ローンを組めない
違反建築物は住宅ローンが組めないなど、資金面でもデメリットが大きくなります。
現行法に適合してない建築物は担保価値がないとみなされるため、銀行は貸し倒れのリスクを恐れて融資に消極的になるためです。
そうなると住宅ローンを利用して購入するのは難しく、自己資金だけで購入せざるをえません。
たとえ自己資金で購入できたとしても、住宅ローンが組めない物件は流動性が低いため、自分が手放すときに買い手がつきづらいでしょう。
売却するためには、違法となっている部分を是正したり売却価格を下げたりしなければならず、売り手側に大きな負担が発生します。
まとめ

建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合で、大きいほど敷地いっぱいに建物を建てられます。
土地によって建ぺい率の上限が設けられているため、新築住宅の購入や中古住宅の購入・リフォームを検討する際は、事前に確認しておきましょう。
一定の要件を満たすと上限が緩和されることもあります。
ちゅうこだて!は、全国の中古住宅の購入情報を検索できるサイトです。
物件概要には建ぺい率など情報も記載しています。
中古住宅を探している方は、ぜひちゅうこだて!をご活用ください。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 理想の中古物件を探したい /
The post 建ぺい率とは何?計算方法や容積率との違いをわかりやすく解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>The post 別荘でも車庫証明は取得できるの?住民票登録のない場所で車を所有する方法 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>リゾート地に限らず、公共機関が脆弱な別荘での生活は、車がないと何かと不便です。
もともと自家用車を所有しているのなら、別荘まで車で行けば問題ありませんが、都会で暮らす方のなかには、そもそも車を所有していない方も多いのではないでしょうか。
このページでは、別荘で車を持つために必要不可欠な、車庫証明を取得するための方法や注意点をご紹介します。
\理想の中古物件を探したい/
別荘で車庫証明が取れるかは管轄の警察署の判断で決まる
結論から言えば、住民票を置いている自宅とは異なる『別荘』の住所で車庫証明が取れるかは、管轄の警察署の判断になります。
別荘の利用頻度や使い方の実態によって、車庫証明取得の可否が判断されます。
別荘の住所で車庫証明を取るときは、別荘の住所を管轄している警察署で車庫証明の取得基準を確認しましょう。
そもそも車庫証明ってなに?
『車庫証明』は正式名称を、普通自動車の場合『自動車保管場所証明書』、軽自動車の場合『自動車保管場所届出書』と言います。
その名のとおり、車の保管場所が確保されていることを警察署長が証明するものです。
車庫証明の取得は、車両購入時だけでなく、所有者の変更があった際や、引っ越しなどで保管場所の住所を変更する際に必要な手続きです。
また、車庫証明がないと車の購入手続きができないほど重要な書類です。
車庫証明の手続きを怠ると、10万円以下の罰金が科される場合もあります。
車庫証明が不要な地域もある
車庫証明は、もともと人口過密地域で路上駐車が問題になったことで生まれた制度です。
そのため、人口が少ないなど、路上駐車の心配が少ない地域では車庫証明が不要なエリアもあります。
『車庫証明不要地域 一覧』とWebで検索すると、全国の車庫証明不要地域が確認できるので確認してみましょう。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください
\理想の中古物件を探したい/
別荘は車庫証明が取りにくいの?
別荘を毎月定期的に利用しているのであれば、車庫証明を取ることはそう難しくありません。
しかし、住民票で居住実態を証明できない別荘で車庫証明取得は、『別荘が本人の持ち物である事を証明する書類』、『別荘の駐車場の使用権を持っている事を証明する書類』などが必要です。
また、警察官による別荘に車庫があるかどうかの実態確認、実際に生活実態があることを証明する公共料金の領収書などの提出が必要です。
公共料金の領収書について
別荘での生活実態を証明するための、公共料金の請求書・領収書は、以下の点に注意しましょう。
- 電気、水道、ガスの請求書または領収書を用意する
- 宛名は車庫証明を申請する本人のもの
- 申請日の直近3ヵ月以内のもの
- 申請する別荘の番地が正確に記載されていること
また、管轄の警察署によって、許容される別荘の利用頻度が異なり、月数日でOKか、月の半分は暮らしていないとNGなのか、判断がまちまちです。
その点で、別荘での車庫証明は取りにくいといわれます。
普通車と軽自動車では手続きが異なる
普通自動車の車庫証明を取得する際は『自動車保管場所証明申請書』、軽自動車を届け出る際は『自動車保管場所届出書』が必要です。
また、申請する別荘が賃貸か自己所有かでも、必要書類や手続き方法が異なります。
| 名称 | 内容 | 賃貸 | 自己所有 |
|---|---|---|---|
| 【普通自動車】 自動車保管場所証明申請書【軽自動車】 自動車保管場所届出書 |
車庫証明を申請するための書類。 車の情報や、保管場所に関する情報を記入する |
○ | ○ |
| 保管場所標章交付申請書 | 自動車に貼り付けるステッカーの交付を受けるために必要な書類 | ○ | ○ |
| 保管場所の所在図・配置図 | 保管場所の位置や配置を示す書類。 (所在図はMAPを印刷したものでも可) |
○ | ○ |
| 保管場所使用権疎明書面 (自認書) |
自身の所有する土地を駐車場として申請する際に必要な書類 | × | ○ |
| 保管場所使用承諾証明書 (または賃貸契約書のコピー) |
他人が所有する土地を駐車場として申請する際に必要な書類 (車庫の所有者の大家さんや管理会社の署名・捺印が必要) 警察署によっては駐車場の賃貸契約書のコピーでも可 |
○ | × |
| 自動車の使用の本拠の位置が確認できるもの | 車の使用者の住所が確認できる書類。(住民票等) ※別荘の場合、公共料金の領収書等 |
× | ○ |
| 収入証紙(手数料) | 申請手数料。2,000円~3,000円前後 (金額は都道府県により異なる) 車庫証明の発行後の保管場所標章の発行に別途500円必要 |
○ | ○ |
| 印鑑 | シャチハタ不可 | ○ | ○ |
※必要書類は別荘の所在地を管轄する警察署、または警視庁のWebサイトから入手しましょう。記載例も掲載されています。
警視庁:保管場所証明申請手続(窓口申請)
警視庁:保管場所届出手続(窓口申請)
別荘で車を持つメリット・デメリット
そもそも、別荘で車を持つメリット・デメリットは以下のようなものがあります。
メリット
●生活のアシが確保できる
公共機関が脆弱な別荘での生活。自家用車があることで行動範囲がグッと広がり、別荘地での生活が充実します。
●整備やメンテナンスをするスペースが確保できる
土地代の高い都会の住宅地で、車をいじれるガレージを持つには多額の予算が必要です。
しかし、土地の広い別荘地での暮らしなら、気兼ねなく車いじりを楽しめます。
デメリット
●車が傷みやすい
常時住んでいない別荘に車を置いておくと、メンテナンスが行き届かず車が傷みやすくなります。
燃料やオイルの劣化や金属の錆、革のカビ、小動物の配線かじりなど、常時使用しない車に起こりがちなトラブルです。
車の傷みを軽減したいなら、ガレージ付きの物件を探してみましょう。
中古住宅・中古一戸建てを探すなら『ちゅうこだて』がおすすめです!
●盗難の危険性が高い
普段目の行き届かない別荘では、盗難被害が発生する確率が高くなります。
ガレージに防犯カメラや警報装置を設置するなどの工夫が必要です。
●お金がかかる
車を所有する場合、車本体の購入費用からはじまり、保険料・車両重量税・車検費用・ガソリン&オイル代・メンテナンス費用など多くの費用がかかります。
別荘で使う車はレンタカーでも良い
車庫証明取得が困難なエリアであったり、車のメンテナンスや維持費の面で不安を感じるなら、別荘で使う車はレンタカーを利用する方法もあります。
年に数えるほどの利用しかないのであれば、都度のレンタカー代のほうが割安です。
自分のライフスタイルに合った車の使い方を模索してみましょう。
まとめ
このページでは、別荘で車庫証明を取得するための方法や注意点をご紹介しました。
別荘で車庫証明を取得するのは、管轄の警察署の方針によって難易度が異なります。
また、利用頻度の低い別荘に車を保管して利用するのはさまざまなリスクが発生します。
別荘での車の所有は、利用頻度を考えて慎重に検討しましょう。
関連記事
引っ越したら車庫証明の変更を忘れずに!手続き・必要書類ガイド
理想の中古住宅・中古一戸建て物件を探す
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください
\理想の中古物件を探したい/
The post 別荘でも車庫証明は取得できるの?住民票登録のない場所で車を所有する方法 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>The post 別荘に火災保険は必要?不要?|知っておきたい保険の入り方 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>加入率が低いといわれる別荘の火災保険加入率。
しかし、別荘も自宅同様に火事や自然災害に合えば被害を受けます。
むしろ、1年の大半が空き家状態の別荘は、被害が大きくなるリスクが高くなります。
このページでは、別荘用火災保険の、必要な理由や保険選びのポイント、火災保険に安く加入するコツなどをお伝えします。
納得の別荘用火災保険を見つけて、リスクに備えましょう。
\ 理想の中古物件を探したい /
そもそも火災保険は義務ではない

火災保険は、自動車の自賠責保険のように法律で加入が義務づけられている強制保険ではなく、加入する・しないを個人が自由に決められる任意保険です。
別荘は建物がなくなっても普段の生活に影響しない特性から、火災保険に加入しない方が多く、加入率は高くないのが現状のようです。
義務ではない火災保険に加入しなければならないケース
では、決して義務ではない火災保険に多くの方が加入しているのはなぜでしょうか?
下記のようなケースでは、火災保険への加入が契約の条件となる現状があるからです。
- 賃貸物件の契約時
- 住宅ローンの契約時
賃貸では大家さんや管理会社、住宅ローンの借り入れの際は銀行など、物件焼失等の不測の事態に対応するため、火災保険の加入が求められます。
別荘でも火災保険に加入しておいたほうが良い理由
賃貸物件にも住宅ローンに利用にも該当しない別荘なら、自分の判断で火災保険に加入する・しないを選択できますが、別荘も火災保険は加入しておくことをおすすめします。
利用頻度が少ないとはいえ、別荘も自宅同様火事や自然災害に合えば、当然被害を受けます。
むしろ、別荘は常時人がいる状況にないため、消火活動などの対応ができず、建物が全焼してしまうこともあるでしょう。
また、放火や不法侵入、建物の老朽化による倒壊なども通常の住宅よりリスクが高い傾向です。
そのような損害に備えて、火災保険は別荘でも加入しておいたほうが得策です。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 理想の中古物件を探したい /
別荘の火災保険選びのポイント

別荘の火災保険選びには、自宅の火災保険選びとは異なるいくつかポイントがあります。
一緒にみていきましょう。
火災保険の種類
別荘にかけられる火災保険は、別荘の使い方で加入できる保険の種類が異なります。
使い方によって、火災保険の“物件種別”が決まり、加入できる火災保険が制限されるからです。
火災保険では、居住物件を『住宅物件』・『一般物件』の2つに分類します。
・住宅物件
居住用のみに使用している建物。
戸建てやマンション、共同住宅でも、居住用のみであれば住宅物件です。
自己所有かつ、季節的に住居として使用し、かつ家財が常備されている場合はこちらに分類されます。
また、転勤等の理由で一時的に空家となっている住居もこちらの区分です。
・一般物件
住居であっても、一つの建物に店舗や事務所などがある建物は、店舗併用住宅とみなされ一般物件扱いです。
また、自ら住む予定がなく、賃貸入居者も募集していない空き家などもこちらに分類されます。
なお、住宅物件と一般物件では、保険料が異なります。
特約は必要?
日頃から家の状態を観察できる自宅とは異なり、年に何度かの訪問になりがちな別荘では、台風や大雪などの自然災害に見舞われた際のアフターフォローが迅速におこなえない傾向にあります。
また、空き家になっている期間が長いため、不法侵入や盗難も起こりやすい状況です。
侵入時には窓が割られたり、家の中が荒らされたりと、物件の破損にもつながります。
そのため、災害や盗難などの特約加入をおすすめします。
保険会社によって、どこまでが補償範囲でどこからが特約なのか範囲がバラバラなので、見積もりをとって比較するのが良いでしょう。
火災のほか、風災・水災・盗難・水漏れ・破損など、ハザードマップや地域の治安などと相談しながら、なんの特約が必要か決めましょう。
地震保険には加入できる?
火災保険と同時加入できる地震保険の対象は、住居用の建物と家財です。
地震保険は火災保険とセットで契約するため、別荘が『住宅用物件』として火災保険に契約している場合は、地震保険に契約できます。
しかし、別荘が『併用住宅物件』や『一般物件』として火災保険に加入する場合は、地震保険に加入ができない場合があります。
詳しくは保険会社に確認しましょう。
個人賠償責任保険は必要?
日本の法律上、失火による火災で周辺の建物に燃え移った場合でも、他人の建物および設備に対して賠償責任は発生しません。
しかし手入れが行き届かず、老朽化した家の一部が強風などで飛散し、隣家や他人の所有物を傷つけたり、人に怪我を負わせるケースも0ではありません。
家の所有者として、損害賠償の責任が発生する場合もあるので、経済的な負担を大きく受けないよう、備えておくにこしたことはないでしょう。
別荘の火災保険に安く加入したいなら

火災保険料はおもに以下のような項目を考慮して、物件ごとに価格が設定されます。
- 構造
- 床面積
- 建築年月
- 建築金額
- 補償範囲
ただ、常時住んでいない別荘に多額の保険料を払うのがもったいないのも確かです。
別荘にかける火災保険は、万が一火災で焼失した場合に備え、片づけの費用をまかなえる必要最低限の保険にするのがおすすめです。
自宅など、通常の住宅では、火災保険金額を、物件評価額の100%で設定するのが一般的です。
ですが、別荘の場合仮に焼失してしまっても、他に住む場所はあるわけですから、新たに建て直しや買い替えをしなくても困りません。
しかし、焼け残った残骸の撤去費用は必要です。
撤去費用をまかなえるだけの保険金が受け取れるよう設定し、月々の保険料を抑えましょう。
おすすめの火災保険は?
別荘にかける火災保険は、保険会社によって保険料が大きく異なります。
また、物件の構造や床面積、建築年月、建築金額、保険に含めたい補償範囲など多くの項目を考慮したうえで、保険料が決まるため、一概にどの火災保険が良いとはいえません。
自分にぴったりの火災保険を見つけるには、一括見積りを利用するなど、3〜5社を目安に内容を見比べながら判断しましょう。
まとめ
別荘の火災保険加入率は低いですが、ローン購入する場合や建物・家財の価値が大きい場合、万が一の際の撤去費用などを支払う蓄えが少ない場合、火災保険の加入を積極的に検討してみましょう。
理想の中古住宅・中古一戸建て物件を探す
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 理想の中古物件を探したい /
The post 別荘に火災保険は必要?不要?|知っておきたい保険の入り方 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>The post 平屋がうるさいといわれる理由は?防音対策やリフォームを解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>シンプルでおしゃれな暮らしが実現できることで人気が高まる平屋ですが、「室内の音と外からの音が気になる」といわれています。
この記事では、平屋がうるさいといわれる理由や対策、リフォームの依頼方法を解説します。
防音にも利用できる補助金もご説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
平屋がうるさいといわれる理由4つ

平屋がうるさいといわれる原因は以下の4つで、いずれも平屋の構造や使い方に起因します。
- 居室とリビングが近い
- 屋根からの音が直接響く
- 道路から居室の距離が近い
- 住宅設備の音が聞こえやすい
居室とリビングが近い
平屋はワンフロアの間取りである関係で、もっとも生活音が出るリビングと、寝室や子ども部屋などの居室が隣接しやすく音が気になりがちです。
これは階段のスペースがないことと、建ぺい率を有効利用することから玄関ホールや廊下などを設けないケースが多いためです。
生活動線が短いという利点の反面、リビングの音を遮る構造物なしに居室へ音が伝わる原因となります。
リビングは、早朝から場合によっては深夜まで家族の出入りがあり、会話や足音を避けることは難しい場所のため、居室に気兼ねしながら過ごすのは苦痛となるでしょう。
屋根からの音が直接響く
平屋には、屋根と居室との間に二階の部屋がありません。
小屋裏や屋根の断熱状況や、屋根の材質にもよりますが、すべての部屋で屋根からの雨音や風の音などが直接聞こえます。
天井の高さが高めに設計されていればいくらか回避はできますが、リフォームで小屋裏を取り払って吹き抜け風にすれば天井の防音が薄くなり、スキップフロアを設けた場合は音源である天井の距離が近くなるため、どちらも感じる音は大きくなってしまいます。
瓦屋根は一番音を吸収するため、スレート屋根でも比較的雨の音はしませんが、ガルバリウム鋼板は金属製のため、雨の音が直接屋内まで響きやすい素材です。
屋根からの音を気にされる場合、ガルバリウム鋼板の屋根は避けるか、何らかの対策が必要です。
道路から居室の距離が近い
平屋は、比較的二階に設けることの多い寝室や子ども部屋などの居室もすべて1階にある関係で、外からの音をうるさく感じることがあります。
これは居室すべてが直接地面に接していることで、道路の車の振動や、外の騒音が届きやすくなるためです。
面した道路の交通状況にもよりますが、現在2階建てにお住まいの方が1階の部屋に寝てみると、よくわかるでしょう。
住宅設備の音が聞こえやすい
住宅のそばにはエアコンの室外機やエコキュート、給湯器、浄化槽のポンプなどの住宅設備が設置されていますが、これらの音が、周囲が静かになる就寝の時間帯に気になる場合があります。
エアコンは近年就寝中も使うことが多く、エコキュートもエアコン同様にヒートポンプの作動音が出ます。
低周波や高周波の音だけでなく、振動も室内に伝わってくるため、対策が必要になることも考えておきましょう。
お金をかけずにすぐできる平屋の防音対策

防音というと、何らかの工事をおこなうことを連想しますが、まず以下のことを試すと、音の問題が改善されることがあります。
あまりお金をかけずに防音の対策をする方法を解説します。
防音グッズによる対策
音源となる住宅設備や家電製品の下に防音ゴムを付け、引きずり音が気になるリビングの椅子には、脚にカバーを付けて、音を小さくしてみましょう。
足音の響きやすい床にはカーペットやウレタンマットを敷いて吸音を試みます。
カーテンを防音のものに替えることや、窓ガラスに振動を防止する素材を貼ったり、ドアに隙間テープなどを貼ったりすることでも、音の問題は改善されることがあります。
音の種類別の対策箇所は、以下を参考にしてください。
| 対策したいこと | 必要な対策箇所 |
|---|---|
| 屋外からの騒音 | 窓・壁の防音 |
| 室内の生活音 | ドア・床・壁の防音 |
| 楽器練習・映画音楽鑑賞 | 防音室の設置 |
家具・家電の置き方
リビングにあるテレビやスピーカーなどの音は壁伝いに伝わる要素が大きいので、可能なら壁から50センチほど離すだけで改善される場合があります。
リビングのなかの音源は間仕切りで囲んだり、アコーディオンカーテンで仕切ったりするなども効果的です。
寝室や子ども部屋のなかから音を遮る場合は、リビング側に本棚やタンスを置くようにしましょう。
その他
お部屋の使い方を決める際に、間取りに合わせて例えば寝室はリビングや道路からなるべく離れた部屋を使うようにしましょう。
平屋の住まい選びの段階で、リビングと居室が廊下、中庭、集中収納で隔てられている間取りの物件を選ぶと、リビングの音がほかの部屋に干渉せず、夜間から早朝にかけての音のストレスが少なくなります。
また、音源となる要素はなるべく同じ場所に集中していることが望ましく、水回りが集中している間取りは家事音を一箇所に集められるため、離れた場所を静かにできるでしょう。
さらに、夜の9時以降はテレビの音を下げるようにするなど、家族のなかで相手を思いやったルール決めをすることも、音の問題の解決につながります。
このほか外からの音の問題は、住まいの購入時に防音対策済みか、幹線道路から離れた物件を探すこと、郊外や地方に引っ越すことで軽減されるでしょう。
子どもの騒ぐ声など、こちらの出す音に気遣うことがストレスで移住を考える方は多いのですが、逆に外からの騒音も静かにできます。
ただし、大型トラックが深夜でも往来する国道沿いは、地方でもかなりの騒音レベルになるため、立地選びは慎重におこないましょう。
うるさい平屋に効く防音リフォーム

前項のような工夫の他に、音を小さくする工事をおこなうこともできます。
防音対策としてリフォームをおこなう場合の施工法を解説します。
室内音の対策
床や壁や天井に使う断熱材を防音効果が高いものに交換、あるいは追加施工することで、音や振動の軽減ができます。
断熱材は本来の目的以外に、吸音の副次的な効果があるためですが、お部屋の快適性や空調の光熱費の節約にもつながるので、おすすめの方法です。
築年数を経た中古一戸建ての場合、防音・断熱はされているけれど、資材や施工の方法が古い場合もあります。
近年断熱の主流となっているのは、グラスウールやロックウールで、これらのほうが、ウレタンフォームより防音性能が高い傾向にあります。
グラスウールとロックウールで吸収する音域が異なるため、生活環境や要望を正しく伝えることで、防音の断熱施工方法を検討してもらいましょう。
屋根からの音の対策
屋根裏にも吸音性のある断熱材を敷き詰めることで、雨音などの防音効果が期待できます。
特に天井を取り払って室内高を高くとる場合は、屋根の防音には要注意です。
音は振動によって伝わるため、振動を抑える制振材を屋根に使うと音が伝わりにくくなります。
例えばガルバリウムなどの厚さが薄く軽量な金属は、剛性が高い反面振動しやすいです。
振動を吸収してくれる制振材を裏打ちすると振動も抑えられ、防音の効果が高まります。
また、屋根に防音効果のある塗料を塗ったり、寝室の上に小屋裏収納やスキップフロアを作ったりすると寝室の静粛性がアップするでしょう。
中古物件を検討する際の屋根素材は、瓦がもっとも静かで、音の問題が少ないです。
外部からの音の対策
窓は音や振動が伝わりやすい場所なので、2重ガラスや気密窓に交換すると、外からの音を小さくする効果があります。
ガラスとガラスの間に真空がある2重の真空ガラスは、防音性に優れているだけでなく、断熱や結露防止効果も改善されるでしょう。
住宅設備の防音策
エコキュート、エアコンの室外機、浄化槽のポンプなどは、隣接する居住空間との関係を考えましょう。
特にエコキュートの室外機は、キッチンの外側に配置するようになっていれば、音の面では比較的安心です。
エアコンの室外機も、設置場所に制約があるものですが、なるべく寝室・子ども部屋から室外機を遠ざけて配置するようにしましょう。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
うるさい平屋の防音リフォームに使える補助金

防音のみを目的とするリフォームの補助金は、用途や対象者が限られています。
しかしその対象とならなくとも、防音のためにリフォームの助成金を受ける方法があります。
防音に関連した補助金がどのようなものかを確認しておきましょう。
騒音のある場所に対する補助金
以下のような場所は音の大きさや平屋かどうかなどには関係なく、騒音の音量が大きいと認定され、防音施工が助成金の対象となります。
- 指定された幹線道路の沿道の近く
- 自衛隊や在日米軍基地の近く
- 空港の近く
詳細は以下ですが、自治体の情報なども含め、該当するか確認してみてください。
| 対象者 | 対象工事 | 助成の度合い |
|---|---|---|
| 幹線道路沿いの居住者 | 「沿道整備道路」に指定された道路の沿道で、特別区により「防音構造に関する条例」が適用された区域内で条件を満たす住宅の防音工事 <東京都の例> 環状七号線 ・環状八号線 ・中原街道 ・笹目通り |
審査した工事費用の4分の3かつ、騒音調査結果に基づく対象室数により、助成限度額が異なる。 |
| 自衛隊/在日米軍基地の飛行場近くの居住者 | 防衛省が定めた「住宅防音工事標準仕方書」によって住宅の防音工事をおこなう場合 | 原則として工事費の全額を助成。 |
| 空港の近くの居住者 | 国交省が告示した「騒音区域内」で、条件を満たす住宅が、基準に定められた防音工事をおこなう場合が対象 | 騒防法に基づき、防音工事費の全額もしくは一部を補助。 |
住宅性能の向上に対する補助金
上記の助成金に該当しなくとも助成金を申請できる方法は、防音や断熱などの住宅性能向上に対する助成金に申請することです。
これは前述のように、同じ施工で防音の効果も得られるためです。
例えば窓の2重化や、屋根の断熱などは防音でも同様の工事をおこないます。
2023年は以下のような助成金が運用されていました。
| 補助金名 | 対象工事 | 補助額 |
|---|---|---|
| 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 15%以上の省エネ効果が見込まれる高性能建材(断熱材・窓・ガラス)を使用した既存住宅のトータル断熱リフォーム、または居間に高性能建材(窓)を用いた断熱リフォーム | <一戸建て住宅の場合> 1住戸あたり120万円を上限額とし、費用の3分の1以内を補助。 ※120万円に加えて、以下の設備に対する補助金あり。 ・家庭用蓄電システム:20万円 ・家庭用蓄熱設備:5万円 ・熱交換型換気設備など:5万円 |
| 次世代省エネ建材の実証支援事業 | <外張り断熱> 外張り断熱工法などで住宅の外壁などを改修し、住宅全体の断熱性能を向上させるリフォーム <内張り断熱> 施工性の向上のために断熱材・下地材が一体となった断熱パネルや、快適性向上に役立つ潜熱蓄熱建材を導入するリフォーム <窓断熱> すべての窓をSグレードの外窓(防火・防風・防犯仕様)にてリフォーム |
<外張り断熱> 一戸建て住宅1住戸あたり300 ~400万円を上限、経費の2分の1以内を補助。 <内張り断熱> 一戸建て住宅:1住戸あたり20~200万円、経費の2分の1以内を補助。 <窓断熱> 一戸建て住宅1住戸あたり150万円を上限、経費の2分の1以内を補助。「任意製品」も併用して改修する場合は200万円が上限。 |
| こどもエコすまい支援事業 【受付終了】 |
<必須工事> ※いずれか必須 ・開口部の断熱改修 ・外壁、屋根・天井または床の断熱改修 ・エコ住宅設備の設置 |
原則1戸あたり30万円(工事の内容や属性に応じて最大60万円)
<子育て世帯または若者夫婦世帯> <一般世帯・子なし可> |
助成金は年度によって実施内容や改廃がある他、年度内でも申し込み定員に達した場合、締め切りとなる可能性がありますので、常に最新の情報を確認するようにしましょう。
防音リフォームを依頼する際の注意点

効果的な防音リフォームをおこなうために、知っておくと良いことがいくつかあります。
防音リフォームを業者に依頼する際の注意点や、NG事項をご説明します。
依頼のための3ステップを意識する
リフォームの施工は、段取りを踏んで進めることでスムースかつ、効果的な工事依頼ができます。
問題点の整理
防音リフォームを依頼する前に、家族で問題点をまとめてみましょう。
「ここに問題がある」「この問題を優先したい」などの整理をしますが、必要なのは例えば予算内で、屋根からの音よりも道路の騒音を優先的に対策したいという話し合いです。
入居時におこなうリフォームの場合は、実際に問題を体験していないため、ご家族で調べた平屋の防音に関する情報を共有したうえで、何を優先するかを考えましょう。
予算の検討
整理された問題点をもとに、おこないたい施工の費用相場を調べ、何社かに相見積もりの打診をした結果から、予算感を詰めていきます。
基本的には相場よりも、見積もりのほうが金額は高めになることが多いので、その理由を各社に確認していきましょう。
近年は資材の費用が高騰しているため、業者によって仕入れルートの違いから、見積金額に差が出ることもあります。
業者選び
業者を選ぶ際は、価格が安いだけでなく以下の点も注意して選びましょう。
提案内容がわかりやすく、質問に誠実に答えてくれ、具体的なアドバイスをくれる会社に依頼するのが良いです。
ホームページの施工実績、ブログの記事の施工例や、お客様の声なども参考にし、質問に対する回答も判断材料にします。
一括査定サイトなどで口コミが確認できれば、参考にするのも良いですが、さまざまな意図の書き込みがあるので、鵜呑みにするのは避けたほうが良いでしょう。
マンションや賃貸物件での制約
賃貸物件の場合は貸し主と話し合いの結果了承を得られる場合を除き、退去時には原状回復する必要があります。
原状回復しなくとも良いとなった場合は、費用をどのようにするかも話し合いましょう。
さらにマンションは賃貸でなく自己所有の場合でも、管理組合規定で改修箇所に制限が設けられているので、確認が必要になります。
リフォームの費用対効果に注意する
リフォームは依頼主と業者との間に希望する効果や、予算の詳細の共有がされていない場合、トラブルとなる可能性があります。
予算の範囲で効果が期待できるかは、しっかり確認の必要がありますが、これから入居する場合の依頼は、効果のビフォーアフターの判断が困難なので特に注意が必要です。
住み始めて音の状況を確認してから、リフォームを依頼しても良いでしょう。
まとめ

平屋がうるさいといわれる理由や対策方法、リフォームの依頼の他、防音に利用できる補助金を解説しました。
音の問題はケースバイケースのため、有効な解決策は千差万別ですが、数百円のグッズで効果が上がる場合もあるため、対策前に音の原因や、家族の要望をよく確認するのが大切です。
平屋の物件をお探しの方へ
ちゅうこだて!では平屋の中古一戸建てを数多くご紹介しています。
築年数や図面ありの物件を絞り込めるため、ぜひ一度ご覧ください。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
The post 平屋がうるさいといわれる理由は?防音対策やリフォームを解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>The post 平屋の屋上を有効活用するためのアイデア|屋外空間の魅力とデメリットを解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>平屋の屋上は広々とした開放感を味わえる魅力的な空間ですが、有効活用されている方は少ないのが現状です。
平屋の屋上は無限の可能性を秘めており、アイデア次第で素晴らしい時間を満喫できます。
この記事では、屋外空間の魅力と平屋の屋上を有効活用するためのアイデアをご紹介します。
平屋の屋上の活用方法を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
平屋の屋上の魅力とは?

陸屋根(ろくやね)の平屋は屋根が水平であるため、屋上が設置できます。
屋上を設置することで、自由に使える面積が増えるなどさまざまなメリットが得られ、平屋の魅力が増幅するでしょう。
ここでは、平屋の屋上の魅力を解説します。
自然光と広々とした開放感
屋上の魅力は開放感があることです。
屋上の広々とした空間は遮る屋根がないため圧迫感がなく、気持ちをリフレッシュできます。
地上から離れているため騒音が軽減され、静かな環境でくつろげます。
日当たりにもよりますが、自然光を浴びられることも魅力です。
適度な日光浴は心身の健康に良い影響を与えます。
日光を浴びると幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンの生成が活性化し、リラックス効果やストレス解消などの効果が期待できます。
自宅の屋上にリラックスできるスペースがあることは、一般の住宅にはない大きな魅力です。
一戸建て住宅の二階や三階に設置されるバルコニーと比べると屋上テラスのほうが広く、広い空間を家族だけのプライベートスペースとして独占できます。
気軽に屋外空間を楽しめる
家にいながら気軽に屋外空間を楽しめることは、屋上の大きな魅力です。
屋上は「ルーフバルコニー」や「屋上テラス」と呼ばれており、家族だけのプライベート空間として、アイデア次第でさまざまな方法で楽しめます。
敷地の関係で広い庭を持てなくても、屋上が庭園になるため、子どもやペットの遊び場として活用できます。
家でキャンプやバーベキューなどを楽しめることも魅力です。
屋上の具体的な活用方法はあとで詳しく解説しますが、創意工夫をすることで活用の可能性は無限に広がります。
屋上を設置するには防水工事や補強工事などの費用がかかりますが、自宅で気軽にアウトドア気分を味わいたい方には、費用対効果は高いといえるでしょう。
平屋の屋上を活用するメリット

平屋の屋上は防水工事や補強工事をおこない建築基準法の基準を満たせば、庭園やリビングスペースとして活用でき、災害時の避難場所にもなります。
ここでは、平屋の屋上を活用するメリットを解説します。
敷地が狭くても屋上に庭園を設けられる
平屋に屋上を設置すると、敷地が狭くても屋上に庭園を設けられます。
都市部では広い庭を持つのは難しいですが、屋上を二つ目の庭にできることはメリットです。
地上の庭よりも広くできる可能性が高く、都市部ではメリットが大きいでしょう。
洗濯物を干すためのスペースにもなり、日当たりや風通しが良ければ洗濯物はしっかりと乾きます。
また、屋上の緑地化も可能です。地球温暖化対策として屋上緑化は進んでおり、病院や工場だけでなく一般住宅でもおこなわれるようになっています。
屋上緑化はヒートアイランド現象の緩和や癒やしの効果、建物の保護効果、省エネルギー効果などが期待でき、室内温度の上昇を軽減し、居住性の向上にもつながります。
屋上をリビングスペースにできる
屋上は庭園としてだけでなく、二つ目のリビングとしても活用できます。
平屋は水平に広がる一つの階層で構成されており、土地の面積に比べて建物の床面積が制約されるケースが多いです。
建物内のリビングスペースが狭くても、屋上を第2のリビングとして活用することで、ゆったりと暮らせます。
屋上は開放感があるため、のんびり読書をしたり、昼寝をしたりするのに最適です。
日当たりが良ければさらに快適に過ごせます。
防水工事や補強工事をおこなえば、テーブルと椅子を置くだけで屋上はリビングになり、配管延長工事をおこなって屋外水栓を設置すると水道も使えます。
屋上バーを設置して、お酒を飲みながらゆったりとくつろぐこともできるでしょう。
災害時の避難場所になる
平屋に屋上を設置することで、水害などの災害時における避難場所として活用できます。
水害時は垂直方向への避難が原則ですが、平屋は上階がないため垂直避難ができません。
しかし、屋上を設置することで垂直避難が可能になります。
屋上を設置すれば、避難場所が身近にあることで安心して暮らせます。自宅の屋上へは迅速に避難でき、屋上は広いため、家族全員やご近所の方も避難できるでしょう。
屋上の設置で安全性が高まることは大きなメリットです。
洪水や高潮、津波、土砂災害のリスクは、国土交通省のハザードマップポータルサイトで確認できます。
災害リスクの高い地域にお住まいの場合は、平屋に屋上の設置をおすすめします。
平屋の屋上を活用するデメリット
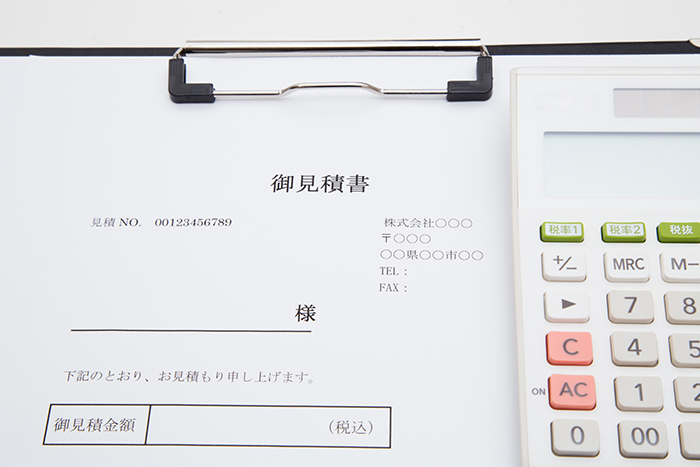
ここまで平屋に屋上を設置する魅力や活用するメリットを紹介しましたが、デメリットも存在します。
ここでは、平屋の屋上を活用するデメリットを解説します。
屋上を設置する際は、メリット・デメリットの両面からの検討が大切です。
工事費がかかる
平屋に屋上を設置するには防水工事や補強工事が必要で、屋上にアクセスするための階段の設置工事も必要です。
屋上を緑地化したり、人工芝を敷設したりする場合も費用がかかります。
工事の内容にもよりますが、100〜300万円程度の工事費が必要です。
建設コストを低く抑えたい場合は、屋上を設置すると工事費が割高になるため、予算内に収まるかを検討しなければなりません。
複数のハウスメーカーや工務店に相談して見積もりを取り、予算内で屋上を設置できるかを確認しましょう。
なお、屋上を設置後も防水工事は定期的におこなう必要があり、将来的に継続してメンテナンス費がかかります。
将来的に発生する費用を含めての検討が大切です。
雨漏りのリスクが高まる
平屋に屋上を設置する際、雨漏りのリスクが高まることは特に注意が必要です。
屋上は陸屋根に設置しますが、陸屋根は水はけが悪い性質を持っています。
陸屋根は水平な屋根のため、三角屋根(切妻屋根)や片流れ屋根のような傾斜がなく、構造上の問題で水はけが悪いのです。
防水工事をしっかりおこなわないと雨漏りが発生し、建物に深刻な損害を与える可能性があります。
防水工事は、適切な材料や施工方法を使用して屋上の水密性を確保するためにおこなわれ、質の高い工事をすることで雨漏りを防げます。
豪雪地帯にお住まいの場合は、雨漏りだけでなく雪の重みもリスク要因になり、耐雪性を確保するための屋根の設計や補強工事が必要です。
定期的にメンテナンスが必要
屋上を設置後も定期的にメンテナンスをおこない、再防水が必要な場合は工事費がかかります。
屋上の水密性を確保して雨漏りを防ぐには、10年程度で再防水が必要です。
定期点検では、防水層のひび割れや剥がれなどの劣化状況を確認します。
劣化が見つかった場合は、早めに修復や再防水工事をおこなうことで、大きな被害を未然に防げます。
屋上を設置後も定期的にメンテナンスをおこない、防水層の状態を良好に保つことが大切です。
再防水工事の費用は、防水工事の種類や施工面積によって異なり、詳細はあとで解説します。
なお、鳥の糞の掃除なども日頃からおこなうことが必要です。
日頃から掃除しておくことで屋上の美観を保て、防水層の保護にもつながります。
夏は暑くて冬は寒い
屋上は屋外環境であるため、季節によって気温が大きく変化し、夏は暑くて冬は寒く、季節によっては快適に過ごせないことがあります。
夏場は強い日差しが屋上の表面で反射し、地上よりも高温になるのが一般的です。
特にアスファルトやコンクリートなどの熱を吸収しやすい床材を使用した場合、屋上はかなりの高温になります。
屋上の温度上昇を抑えるには適切な床材を選び、日除けを設置するなどの対策が必要です。
冬場の屋上は地上よりも寒冷になる傾向があります。
適切な断熱材を使用し、暖房器具などを用意して寒さ対策をおこないましょう。
なお、豪雪地帯では屋上に雪が積もるため、冬場は使えなくなります。
地域の気象の変化に応じて、適切な対策を講じることが大切です。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
平屋の屋上を有効活用するためのアイデア

平屋の屋上は家族専用のプライベート空間であり、さまざまな方法で有効活用ができます。
ここでは、平屋の屋上を有効活用するためのアイデアをいくつかご紹介します。
活用方法は無限にあり、自分や家族にとって最適な活用方法を見つけましょう。
バーベキューを楽しむ
屋上で家族や友人とバーベキューを楽しむのは、定番の活用方法でしょう。
わざわざキャンプ場に行かなくても自宅でバーベキューを楽しめるのは大きな魅力です。
普段使っているバーベキューグッズを屋上に運ぶだけでバーベキューを楽しめます。
屋外水栓を設置して水道を使えるようにすると大変便利です。
水道を使えない場合は、1階のキッチンで水をウォータータンクに入れて屋上に運んで使用します。
自宅のキッチンを使えることは屋上ならではのメリットです。
なお、住宅密集地では、煙や騒音で近所迷惑にならないよう注意しましょう。
ガーデニングを楽しむ
自宅のバルコニーでガーデニングをする方は多いですが、屋上だと広いスペースでガーデニングや家庭菜園を楽しめます。
屋上でガーデニングをするなら、水道を使えるようにしておくと大変便利です。
水道設備を設置しない場合は、水やりの際は下階から水を運ぶ必要があります。
屋上は虫があまり寄ってこないことがメリットです。
野生動物に植物を荒らされる心配もなく、快適な環境で草花や野菜を育てられます。
なお、屋上でガーデニングをする際は、台風や強風への備えが欠かせません。
プランターやガーデニング用品が風で飛ばされないよう、適切な対策が必要です。
テントを設置してアウトドア気分を味わう
屋上にテントを張ると、プチキャンプを楽しめます。
屋上だと下階のキッチンで調理ができるため、特に何を準備するまでもなく、思い立ったらテントを張るだけですぐにアウトドア気分を味わえます。
急に天候が悪化したり体調が悪くなったりしたときも、すぐに撤収できるので安心です。
キャンプの経験が少ない方はテントの張り方などを練習でき、本番に備えられます。
通行人の視線が気にならないことも、屋上ならではのメリットです。
夜になると開放感のある屋上のテントから星空を眺められ、ゆったりとした時間を過ごせます。
ミニプールを設置してリゾート気分を味わう
屋上にミニプールや大きなビニールプールを設置すると、家にいながらリゾート気分やレジャー気分を味わえます。
ビーチパラソルやサマーベッドなどを設置すると、さらに気分が盛り上がるでしょう。
フェンスを設置すると外からは見えず、気兼ねなくレジャー気分を満喫できます。
パラペット(手すり壁)にすると安全性が増し、目隠し効果は抜群です。
周辺にマンションなどの高層建築物がある場合は、タープやオーニングを張ると対処できます。
ガーデンライトを設置すると夜でもリゾート気分を味わえ、日常の喧騒から離れた時間を過ごせます。
屋上バーを設置してリラックスする
屋上バー(ルーフトップバー)を設置すると、プライベート空間でお酒を飲みながらリラックスできます。
キャンドルライトやアウトドア用ランタン、ガーデンライトなどを用意して、穏やかなピアノジャズをBGMで流すとおしゃれでモダンな雰囲気に浸れます。
自宅にいながら非日常的な雰囲気を味わえるのは、屋上バーならではの魅力です。
必要なものはテーブルと椅子だけで、料理やお酒、おつまみはキッチンから運びます。
煙や騒音による近所迷惑が心配で屋上バーベキューを断念した場合でも、屋上バーならマナーを守って適切な配慮をすれば問題にはならないでしょう。
子どもやペットの遊び場にする
小さな子どもがいる家庭では、屋上を子どもの遊び場として活用できます。
屋上だと交通事故や不審者などの心配はなく、子どもは安心して遊べます。
ただし、落下しないよう徹底した安全対策が必要です。
必ず頑丈な壁やフェンスを設置しましょう。
小型犬や超小型犬などのペットを飼っている家庭ならば、屋上をドッグランにすることもできます。
屋上にドッグランを作るには、人工芝の敷設がおすすめです。
水道設備もあったほうが良いでしょう。
愛犬が思う存分遊び、勢いあまって落下しないよう、フェンスを高くするなどの安全対策は欠かせません。
開放的な空間でヨガやエクササイズをする
屋上にヨガマットを敷くだけで、開放的な空間でヨガやエクササイズを楽しめます。
屋上だと人目を気にせず集中して取り組めるのがメリットです。
ヨガやエクササイズは在宅ワークの気分転換にも最適で、仕事で疲れたときは屋上に行ってリフレッシュできます。
お金をかけずにヨガやエクササイズを始めたい方にも最適です。
ヨガスクールやジムに通う手間も省け、気が向いたときに屋上に行くとすぐに始められます。
日の出前の静かな時間帯には、屋上は目を閉じて瞑想をするのにも適します。
朝日を浴びると清々しい気持ちになるでしょう。
収納スペースにする
屋上に物置を設置すると収納スペースになります。
あまり使わない荷物を屋上の物置に収納すると、平屋の居住空間をより広く使えます。
コンテナハウスなどに荷物を収納するとお金がかかりますが、屋上の物置だと費用はかからず、いつでも荷物が出し入れ可能です。
注意点として、屋上に物置を設置する際は下地にアンカーを打ち込まなければならず、しっかりと固定できないと設置はできません。
固定できないと強風で物置が吹き飛ばされることがありとても危険です。
屋上に物置を設置する際は専門家に相談し、設置できるかを確認しましょう。
平屋の屋上を有効活用するのに役立つアイテム

防水工事や補強工事をおこなって、壁の設置などの安全対策を施せば平屋の屋上を活用できるようになります。
ここでは、平屋の屋上を有効活用するのに役立つアイテムをご紹介します。必要に応じて設置を検討しましょう。
オーニングやサンシェード
夏場は強い日差しが屋上の表面で反射して暑くなるため、オーニングやサンシェードなどの日除けアイテムの設置がおすすめです。
オーニングは布製のひさしのようなもので、オーニングの下に日陰ができて暑さをしのげます。
サンシェードは布製の日除けで、オーニングと同じように直射日光を遮断して日陰を作ります。
オーニングはサンシェードよりも頑丈で、雨除けにもなるのが特徴です。
屋上に設置するなら、頑丈で雨除けにもなるオーニングをおすすめします。
周辺に高層建築物がある場合、平屋の屋上は上から丸見えになりますが、オーニングやサンシェードは目隠しとしての機能も果たします。
特にオーニングは日除けや雨除け、目隠しにもなるため、設置するメリットは大きいです。
屋外用防水コンセント
屋外用防水コンセントがあると、屋上で電化製品を使えるので大変便利です。
照明や調理器具などはコンセントがないと使えないため、屋上で調理をするのであれば必ず設置しましょう。
屋上に防水機能のない普通のコンセントを設置すると、漏電して感電することがあり、大変危険です。
必ず屋外用防水コンセントを設置するようにしてください。
なお、屋外用防水コンセントは設置できる場所が決まっているため、コードリールも必要です。
コードリールがあるとコードを延長できるため、コンセントから離れていても電化製品を使えます。
屋外用防水コンセントを設置するには電気工事士の資格が必要であり、電気工事業者に依頼すると設置してもらえます。
水栓
屋外水栓を取り付けると、屋上で水道が使えるようになります。
屋上でガーデニングをする際は水道を使えると水やりがとても楽になります。
屋上で水道が使えないと、下階の洗面台からホースをつなぐか、バケツなどに水を入れて屋上まで運ばなければなりません。
手間と労力がかかるため、屋上でガーデニングをする際は屋外水栓の取り付けをおすすめします。
バーベキューや屋上キャンプをする際も、水道が使えると大変便利です。
ドッグランを作る際も水道は必要になってきます。
水栓の取り付けは給水装置工事主任技術者の資格が必要で、水道業者に依頼すると取り付けてもらえます。
工事費の相場は2~8万円で、正確な料金は見積もりの取得が必要です。
家庭用高圧洗浄機
家庭用高圧洗浄機があると、屋上の掃除がとても楽になります。
屋上の美観を保つには、定期的な掃除が欠かせません。また掃除をすることで防水層の保護につながります。
屋上にゴミが堆積すると防水層が損傷し雨漏りのリスクが高まり大変危険です。
家庭用高圧洗浄機を使用すると、掃除の労力と時間が大きく軽減します。
床だけでなく落下防止用の壁の掃除にも使えるため、家庭用高圧洗浄機は必需品といえるでしょう。
なお、屋上で家庭用高圧洗浄機を使用するにはコンセントが必要です。
給水方式は給水タンク式、自吸式、水道接続式があり、給水タンク式と自吸式は屋上に水栓がなくても使えます。
家庭用高圧洗浄機の価格は1万円台~数万円で、高機能になるほど価格も高くなります。
ジョイントマット
屋上にジョイントマットを敷くと水はけが良くなります。
クッション性があるため、人工芝を敷く際にも活用できます。
屋上にドッグランを作る際は、人工芝を敷設する際にジョイントマットを敷いておくとクッション性が良くなるのでおすすめです。
ジョイントマットの素材はさまざまで、EVA樹脂やPE樹脂、コルク、ウレタンなどがあります。
ジョイントマットは撥水性があるため雨水が溜まりにくくなり、通気性やクッション性も向上します。
ただし、強力な水はけ改善効果はなく、大雨や豪雨に対しての効果は限定的です。
劇的な効果はありませんが、水はけを良くしたい場合はEVA樹脂やPE樹脂のジョイントマットを敷いておくと良いでしょう。
ガーデンライト
ガーデンライトがあると夜の屋上がおしゃれな空間になります。
殺風景な雰囲気の屋上に暖かい明かりのガーデンライトを置くと、雰囲気が大きく変わります。屋上バーを設置する際はガーデンライトがおすすめです。
太陽光で充電するソーラーライトは電源不要で、日が落ちて暗くなると自動的にライトアップされます。
日が昇って明るくなると自動的にライトは消えます。
ソーラーライトはさまざまな種類があり、100均でも購入可能です。
必需品ではありませんが、夜の屋上の雰囲気を良くしたい場合は、100均などで何個か購入すると良いでしょう。
安物感が気になる場合は、ワイングラスのなかにソーラーライトを入れるとゴージャスな雰囲気になります。
防水工事の費用の目安

平屋に屋上を設置するリスク要因である雨漏りを防ぐには、防水工事が欠かせません。
防水工事は定期的におこなわなければならず、どの程度の費用がかかるのかを知っておく必要があります。
ここでは、防水工事の費用の目安を解説します。
ウレタン防水
ウレタン防水の費用相場は1平米あたり2,500~7,000円程度です。
屋上の面積が30坪の場合だと、防水工事費の総額は25~70万円程度になります。
ウレタン防水の耐用年数は約10~13年であり、10~13年毎に再防水工事が必要になってきます。
ウレタン防水とは、プラスチックの一種である液体状のウレタン樹脂を塗り重ねることで防水層を形成する防水工法です。
ウレタン樹脂は、柔軟性や耐久性、耐水性に優れた素材であり、屋上やベランダ、バルコニーなどの防水に広く用いられています。
ウレタン防水はコストパフォーマンスに優れた防水工法であり、補修時に選ばれることが多く、施工が容易で短期間で施工できます。
建物のさまざまな部位で使用されますが、完全に硬化し水密性を発揮するまでに時間がかかる点がデメリットです。
塩ビシート防水
塩ビシート防水の費用相場は1平米あたり2,100~7,500円程度です。
屋上の面積が30坪の場合だと、防水工事費の総額は20万~75万円程度になります。
塩ビシート防水の耐用年数は約12~15年であり、12~15年毎に再防水工事が必要になってきます。
塩ビシート防水とは、塩ビ(PVC)樹脂から作られた防水材料で防水層を形成する防水工法です。
塩ビ樹脂は紫外線や気象条件、化学物質に対して耐性があり、屋外での使用に適しています。
塩ビシートは優れた耐水性を持ち、水漏れを防ぐのに効果を発揮します。
塩ビシートは屋上の防水に広く使用されており、屋上庭園やバルコニー、テラスなどの屋外空間を防水するのに最適です。
地下室やプールの防水にも適しており、水密性を発揮します。
FRP防水
FRP防水の費用相場は1平米あたり4,000~7,500円程度です。
屋上の面積が30坪の場合だと、防水工事費の総額は40~75万円程度になります。
FRP防水の耐用年数は約10~15年であり、10~15年毎に再防水工事が必要になってきます。
FRP防水とは、ガラス繊維で強化されたプラスチック(FRP)を使用して防水層を形成する防水工法です。
FRPは紫外線や気象条件に対して優れた耐性があり、屋外環境での使用に適しています。
ガラス繊維による強化プラスチックはとても強固で、建築物の荷重に耐える能力があります。
FRP防水は屋上の防水に広く使用されており、屋上庭園やバルコニー、テラスなどの屋外空間を防水するのに最適です。
FRPは耐薬品性が高いため、化学施設や処理プラントの防水に使用されることもあります。
アスファルト防水
アスファルト防水の費用相場は1平米あたり5,500~8,000円程度です。
屋上の面積が30坪の場合だと、防水工事費の総額は55~80万円程度になります。
アスファルト防水の耐用年数は約12~20年であり、12~20年毎に再防水工事が必要になってきます。
アスファルト防水とは、液体状のアスファルトを塗り重ねることで防水層を形成する防水工法です。
アスファルトは、耐久性や耐水性、耐候性に優れた素材であり、屋上やベランダ、バルコニーなどの防水に広く用いられています。
地下室や地下駐車場の防水にも使用されており、長期間にわたって効力を保ちます。
施工が容易で短期間で施工でき、コストパフォーマンスに優れた防水工法です。
アスファルトを溶融して塗布する熱工法と、常温で塗布する常温工法、トーチバーナーで溶着するトーチ工法があります。
まとめ

平屋の屋上は防水工事や補強工事をすると、さまざまな方法で活用できる魅力的な屋外空間になります。
定番のバーベキューやガーデニングの他、プチキャンプや屋上バー、ドッグランなどにも活用可能です。
オーニングやコンセント、水栓などを設置すると、有効活用の幅が広がります。
注意点として、平屋に屋上を設置すると雨漏りのリスクが高まるため、10年に1回程度の再防水工事が欠かせません。
平屋の物件をお探しの方へ
ちゅうこだて!は、様々な中古一戸建てをご紹介しています。
屋上テラス付きの平屋を探している方は、お目当ての物件を探してみてはいかがでしょうか。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
The post 平屋の屋上を有効活用するためのアイデア|屋外空間の魅力とデメリットを解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>The post 平屋にトイレを二つ設置する必要性とは?メリット・デメリットや間取り例を解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>平屋住宅を建てる際は、トイレを二つ設置する必要があるのか、判断が難しい場合があります。
トイレを二つ設置すると間取りが狭くなり、費用もかかるため、メリット・デメリットを考慮しての総合的な検討が必要です。
この記事では、平屋にトイレを二つ設置する必要性とメリット・デメリットを解説します。
トイレを二つ設置する必要性があるかを判断できるようになるでしょう。
\ 平屋の中古物件を探したい /
平屋にトイレを二つ設置するメリット

平屋にトイレを二つ設置するかで迷っている場合は、二つ設置することのメリット・デメリットを知っておくと判断材料になります。
まずは、平屋にトイレを二つ設置するメリットから見てみましょう。
生活利便性が向上する
平屋にトイレを二つ設置することで生活利便性が向上します。
二つのトイレがあると、誰かがトイレを使っていても、空いているもう一つのトイレを使用できます。
特に朝のトイレラッシュ時にはトイレが二つあると大変便利です。
足腰の弱い高齢者は近くにあるトイレを使用できることもメリットでしょう。
足腰の弱い高齢者は少しの距離を歩くのも大変です。
トイレが遠いと移動中に転倒して怪我をすることがありますが、近いほうのトイレを使用することで転倒事故を防げます。
来客が多い家庭もトイレが二つあると便利です。
来客があっても家族は気兼ねなく別のトイレを使えます。
また、ホームパーティーや法事などで来客が多いときも、トイレが二つあるとトイレラッシュを防げます。
トイレの使い分けができる
トイレが二つあると、家族構成や生活スタイルに合わせて使い分けができます。
例えば男女や、来客用と家族用など、使い分けの方法はさまざまです。
高齢者がいる場合は一つを高齢者専用にして、背もたれやひじ掛け、てすりなどを取り付けると安全かつ快適に使用でき、介護も楽になるでしょう。
車椅子で生活している方が家族にいる場合は、車椅子対応のトイレを用意できます。
また、家族が新型コロナウイルス感染症などに感染した場合は、トイレを使い分けることで家庭内感染を防げます。
このように、二つのトイレを使い分けることは、生活の質と安全性を向上させる点で有益であることが多いです。
トイレが故障しても安心
平屋にトイレが二つあると、トイレが故障しても安心です。
トイレが一つしかないと、故障したときは家でトイレが使えなくなり不便極まりありません。
近所のコンビニや公共施設などのトイレを使うしかないでしょう。
トイレが故障した場合、修理や交換に時間がかかることがあります。
トイレ修理はプロに頼むと30分~1時間程度で終わるのが通常です。
しかし、スマートフォンなどの固形物をトイレに流してしまい、奥のほうまで流れて詰まるとかなりの難作業になります。
便器を脱着しなければ取り出せないこともあり、修理に時間がかかることもあるでしょう。
トイレの故障は頻繁に起こるわけではありませんが、トイレが二つあると万が一の緊急事態に備えられます。
平屋にトイレを二つ設置するデメリット

平屋にトイレを二つ設置すると、生活利便性や安全性、快適性などが向上しますが、追加の設置費用がかかるなどのデメリットも存在します。
ここでは、平屋にトイレを二つ設置するデメリットを解説します。
追加の建設コストがかかる
平屋にトイレを二つ設置すると生活が便利になる反面、追加の建設コストがかかります。
トイレ本体は温水洗浄付きでも5万円程度ですが、取付工事や配管工事、排水設備の調整などが必要になってきます。
トイレを新設・増設する場合の費用相場は、40~100万円程度です。
2階建ての場合は、1階と2階と同じ位置にトイレを設置すると配管工事費を低く抑えられます。
しかし、平屋の場合は配管を左右に振り分けなければならず、工事費は2階建てよりも割高になります。
工事費が100万円以上になる可能性もあり、費用対効果の検討が必要です。
平屋にトイレを二つ設置するとさまざまなメリットが得られますが、費用をかけてまで二つのトイレを設置する価値があるかどうかを検討しましょう。
間取りが狭くなる
平屋にトイレを二つ設置すると、トイレのスペースだけ間取りが狭くなります。
一般的なトイレスペースは0.4坪(78cm×123.5cm)、0.5坪(78cm×169cm)、0.75坪(123.5cm×169cm)、1坪(169cm×169cm)の4種類です。
一般的な一戸建て住宅は0.5坪、広めの一戸建て住宅は0.75坪、バリアフリー対応だと1坪のスペースが必要で、その分だけ間取りが狭くなってしまいます。
0.4~1坪のスペースがあれば、大型の収納スペースなどを設置できるでしょう。
平屋は居住スペースが水平方向に広がるため、2階建ての一戸建て住宅にトイレを二つ設置するよりも間取りに及ぼす影響は大きいです。
トイレ掃除の負担が2倍になる
トイレを二つ設置すると生活が便利になりますが、トイレ掃除の負担は2倍になります。
軽い汚れを落とすだけなら短時間で終わりますが、衛生状態を保つには週に1回、15分程度の掃除が必要です。
便器や便座、タンク、床、壁などを掃除しなければならず、二つのトイレを掃除するのは手間と時間がかかり、面倒に感じることもあるでしょう。
また、トイレの数が増えれば、故障したときのメンテナンス費用や交換費用も高額になります。
新築時に二つのトイレを設置した場合、経年劣化は同時に進行するため、メンテナンスや交換の時期が重なってしまうこともあります。
平屋にトイレを二つ設置する際は、掃除の手間やメンテナンスも考慮して検討しましょう。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
平屋に一つのトイレしかない場合に生じる問題点と対策

さまざまなデメリットを考慮して平屋にトイレを二つ設置せず、トイレを一つしか設置しなかった場合はどのような問題が生じるのでしょうか?
ここでは、平屋に一つのトイレしかない場合に生じる問題点を解説します。
平屋に一つのトイレしかない場合に生じる問題点
平屋に一つのトイレしかないと、朝のトイレラッシュや故障などの緊急事態に対処しにくいことが問題です。
トイレの故障は頻繁に起こることはありませんが、世帯人数が多くて生活リズムが重なる場合、朝のトイレラッシュは深刻な問題になるかもしれません。
また、家族に高齢者がいる場合は、高齢者用のトイレを用意しなければ使いづらい場合があります。
問題点は家族構成や生活スタイルによって異なりますが、二つ設置する場合と比べると生活利便性は低下するでしょう。
平屋に一つのトイレしかない場合の対策
平屋に一つのトイレしかない場合、緊急時に備えて簡易トイレを準備しておくなどの対策が必要です。
朝のトイレラッシュは、話し合って順番を決めたり、独占しないように注意したりするしかないでしょう。
有効な対策はないため、建ててから後悔しないよう、トイレを一つにするか二つにするかを決めることが大切です。
今は二つのトイレは必要なくても、子どもの成長や介護などの将来のニーズも含めて検討しましょう。
平屋にトイレを二つ設置するのがおすすめのケース

必要なトイレの数は、家族構成や生活スタイルによって異なります。
ここでは、平屋にトイレを二つ設置するのがおすすめのケースをご紹介します。
以下のケースに該当する場合、トイレを二つ設置するメリットが大きいです。
家族の人数が多い
家族の人数が多い場合はトイレが二つあると便利です。
トイレが二つあると、トイレラッシュの問題は解決するでしょう。
小さな子どもや高齢者がいる家庭は、トイレが二つあると利便性が高まります。
小さな子どもはトイレを我慢できない場合があり、高齢者は頻尿になるとトイレの回数が増えます。
今は二つのトイレの必要性を感じなくても、出産の予定があったり、親の介護が予想されたりする場合は、二つのトイレの設置を検討しましょう。
ゆっくりトイレを使いたい方がいる
トイレのなかで本を読みたいなど、家族のなかにゆっくりトイレを使いたい方がいる場合は、トイレを二つ設置すると良いでしょう。
トイレが二つあると、家族に気兼ねすることなく、ゆっくりとプライベートな時間を楽しめます。
高齢者はトイレに時間がかかるため、高齢者がいる家庭はトイレが二つあるのが望ましいです。
高齢者専用のバリアフリーのトイレがあると、要介護状態になった場合は高齢者と家族の双方にとってメリットがあります。
平屋にトイレを二つ設置しないのがおすすめのケース

トイレの数を決める際は、予算や費用対効果の検討が大切です。
以下に該当する場合は、トイレを二つ設置するのはおすすめできません。
ここでは、平屋にトイレを二つ設置しないほうがおすすめのケースをご紹介します。
低コストで家を建てたい
トイレを二つ設置すると建設コストが高くなるため、低コストで家を建てたい場合はトイレを二つ設置しないほうがおすすめです。
平屋の場合、トイレを増設すると100万円以上の費用がかかる場合があります。
トイレを二つにすることの費用対効果を考え、高額な費用に見合うだけの価値がないと判断できれば、二つのトイレを設置する必要はありません。
トイレを二つ設置しないことで建設コストを削減でき、将来のメンテナンス費も低く抑えられます。
家族の人数が少ない
二人暮らしなど家族の人数が少ない場合も、トイレを二つ設置しないほうがおすすめです。
近い将来、結婚などで子どもが独立して夫婦の二人暮らしになるような場合も、トイレは一つあれば十分でしょう。
三人家族でも、トイレは一つあれば十分な場合があります。
子どもの誕生や親との同居など、将来的に家族が増えることも考慮し、必要性がなければトイレは一つにすると良いでしょう。
特にメリットがなければ、あえてトイレを二つ設置する必要はありません。
トイレの数は家族構成や生活様式に応じて決める

二つのトイレがいるかいらないかは、家族構成や生活様式によって異なります。
大家族や高齢者がいる家庭、車椅子で生活している方がいる家庭などは、二つのトイレがあると安全性や生活利便性が向上します。
家族の具体的なニーズを考慮して、トイレの数を決めましょう。
二つのトイレを設置する場合、メリットとデメリット、費用と利便性のバランスの検討が重要です。
メリットとデメリットを検討し、デメリットよりもメリットのほうが大きければ、お金をかけてでも二つのトイレを設置する価値はあります。
費用と利便性のバランスを検討し、費用対効果が高いと判断できれば、トイレを二つ設置することをおすすめします。
家族とよく話し合って決めてください。
平屋にトイレを二つ設置する際の間取り例
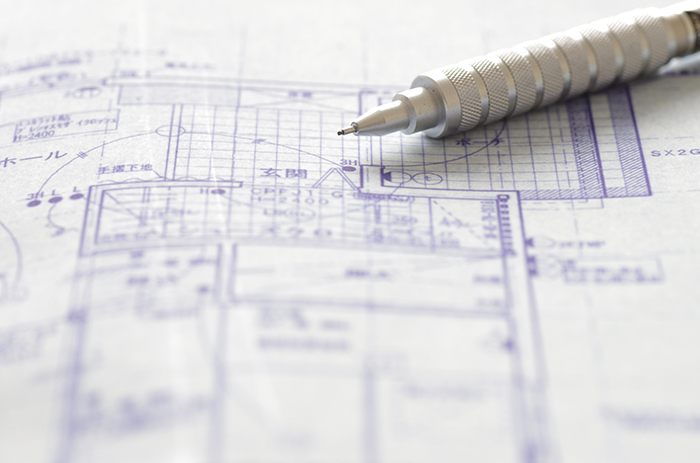
平屋にトイレを二つ設置する際の間取り例は、住宅メーカーのWebサイトやブログなどに掲載されています。
さまざまな間取り例を調べると、理想の間取りが見えてくるでしょう。
ここでは、平屋にトイレを二つ設置する際の間取り例をご紹介します。
4LDKの間取り例
平屋にトイレを二つ設置する30坪4LDKの間取り例として、LDKを中心に玄関ホールの近くにトイレを一つ設置し、奥の和室の近くにもう一つのトイレを設置する方法があります。
奥の和室で居住している高齢者は遠くまで歩かなくても、近くのトイレを使用できます。
LDKからは二つのトイレを使用でき、生活動線の効率化ができるでしょう。
また、玄関ホール側のトイレと水回りをまとめられ、建設コストの削減にもつながります。
平屋にトイレを二つ設置する際は、生活動線や水回りをまとめることを考慮して設計するのがポイントです。
なお、家相では、鬼門(北東)・裏鬼門(南西)にトイレを配置するのは凶とされます。
科学的根拠はありませんが、家相を気にする方は北東と南西にはトイレを配置しないことをおすすめします。
3LDKの間取り例
平屋にトイレを二つ設置する28坪3LDKの間取り例としては、LDKを中心に左側に6畳の洋室を二部屋、右側に6畳の洋室または和室を一部屋配置する方法があります。
トイレはLDKの真上に一つ、右側の洋室または和室の近くに一つ設置します。
このような間取りは30坪4LDKの間取りと同様に、生活動線の効率化と水回りの集約化ができます。
LDKからは二つのトイレを使用でき、トイレラッシュが軽減されるでしょう。
足腰の弱い高齢者は右側の部屋で暮らすと、いつでも近くのトイレを使用できます。
トイレを二つ設置することで、3LDKでも二世帯の同居が可能になります。
家相は間取り30坪4LDKの場合と同様に、気になる方は鬼門と裏鬼門にはトイレを設置しないようにしましょう。
まとめ

平屋にトイレを二つ設置する必要性は、家族構成や生活スタイルによって決まります。
世帯人数が多い場合や高齢者と同居している家庭は、平屋にトイレを二つ設置するのがおすすめです。
世帯人数が少ない家庭や建設コストを抑えたい場合は、トイレは一つで十分でしょう。
トイレを二つ設置すると100万円以上の費用がかかる場合があり、建設コストが割高になります。
費用を低く抑えるのであれば、中古も選択肢に含めるのがおすすめです。
平屋の物件をお探しの方へ
ちゅうこだて!は様々な中古一戸建てをご紹介しています。
トイレ二つ付きの平屋などお目当ての物件を探してみてはいかがでしょうか
新築にこだわらないのであれば大変お得です。ぜひ確認してみてください。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
The post 平屋にトイレを二つ設置する必要性とは?メリット・デメリットや間取り例を解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>The post 平屋にロフトを設けるメリット・デメリットとは?間取り例と注意点を解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>平屋にロフトを設けるとデッドスペースの有効活用が図れるなどのメリットが得られます。
しかし、一般の居室にはないデメリットも存在するため、費用対効果などを考慮して総合的な検討が必要です。
この記事では、平屋にロフトを設けるメリット・デメリットを解説します。
平屋にロフトを設置するかで悩んでいる方は、判断材料になるでしょう。
\ 平屋の中古物件を探したい /
ロフト付き平屋の特徴と魅力

ロフト付き平屋は、平屋とロフトの両方の特徴を併せ持っています。
ここでは、平屋とロフトのそれぞれの特徴と魅力を解説します。
両方の特徴と魅力を知ることで、ロフト付き平屋とはどのような住宅であるかがわかるようになるでしょう。
平屋の特徴と魅力
平屋住宅とは1階建ての家であり、ワンフロアにすべての空間を集約できるのが特徴です。
住空間は水平方向に広がり、階段のないバリアフリーで高齢者も安心して暮らせます。
家全体を見渡せるため子育てが楽になるなど、2階建てよりも快適に暮らせることもあります。
また、平屋の住空間は室外とのつながりが強く、テラスや庭などのアウトドアスペースと自然に統合されることが多いです。
天井が高いため、ロフトを設置すると空間の有効活用が図れます。
ロフトの特徴と魅力
ロフトとは、住宅の部屋と天井の間の空間を利用した屋根裏スペースのことです。
建築基準法では「小屋裏物置等」とされており、平屋に設置すると天井裏のスペースを有効活用できます。
天井高1.4m以下、床面積は下の階の2分の1未満、コンセントは一つだけなどの制約はありますが、アイデア次第で多様な用途に使用可能なスペースです。
ロフトを設置するとおしゃれな雰囲気になるなど魅力は多いですが、熱がこもりやすく暑いなどのデメリットもあります。
ロフトの活用アイデア

ロフトはアイデア次第で、さまざまな用途に活用できます。
ロフト付きの家に住んでいる方は、ブログやSNSなどで自身の活用方法を紹介しています。
ここでは、一般的なロフトの活用方法をご紹介しますので、参考にしてみてください。
大きめの収納スペース
ロフトは法律上は「小屋裏物置等」であり、大きめの収納スペースとして活用できます。
下階の約半分のスペースを確保できるため、コンテナハウス並みの広さです。
季節家電やあまり使わない物をロフトに収納すると、住空間が広くなり快適に暮らせます。
ホームパーティーなどを開催する際は、荷物を一時的にロフトに収納すると部屋を広く使えます。
平屋は居住空間が限られているため、ロフトに物を収納できるメリットは大きいです。
子ども部屋や趣味の部屋
ロフトは子ども部屋や趣味の部屋として活用できます。
ロフトを子ども部屋にすると下の階から見渡せるため、いつでも子どもの様子を確認できます。
ロフトは秘密基地のような雰囲気があるため、好奇心が旺盛な子どもにはうってつけです。
子どもだけでなく、ロフトは大人にとっても秘密基地のようなもので、趣味を楽しむ部屋として活用できます。
ロフトをホームシアターにして、映画やビデオなどを楽しむのも良いでしょう。
書斎や寝室
ロフトは天井が低いため集中しやすく、書斎やテレワークをする仕事部屋などとしても活用できます。
仕事をするのに必要な物だけを置くと気が散らず、集中して仕事に取り組めます。
テレワーク中のWeb会議などにも最適な空間です。
ロフトはベッドを置くと寝室としても使えます。
秘密基地のようなベッドルームは人気が高く、ロフトの活用方法の定番です。
また、下の階のベッドをロフトに置くと平屋の居住空間が広くなり、より快適に暮らせます。
平屋にロフトを設けるメリット

平屋の住空間は水平方向に広がるのが特徴ですが、ロフトを設けると住空間は垂直方向にも拡大されます。
ロフトを上手に活用すると、平屋でありながら2階建てのような雰囲気の住宅になるでしょう。
ここでは、平屋にロフトを設けるメリットをご紹介します。
屋根裏のスペースを有効活用できる
デッドスペースである屋根裏を有効活用できることは、ロフトを設ける大きなメリットです。
高い天井は平屋の魅力の一つですが、デッドスペースになることはデメリットともいえます。
床面積が狭くなりがちな平屋で限られた空間を有効活用したい方にとって、ロフトを設けることは賢明な選択です。
30坪の平屋だと最大約15坪の空間を新たに活用できるため、居住性が向上します。
屋根裏スペースの有効活用には無限の可能性があり、家族のニーズや住宅のデザインに合わせてさまざまな方法で活用できます。
先述したように、書斎や仕事部屋、寝室、子どもの遊び場などさまざまな活用方法があり、どのように活用するかを考えるだけで夢が膨らむでしょう。
要件を満たせば固定資産税の課税対象面積に含まれない
天井高1.4m以下、床面積は下の階の2分の1未満などの要件を満たすと、ロフトは固定資産税の課税対象面積に含まれません。
これにより、節税効果が得られることはロフトを設けるメリットです。
下階の約半分の広いスペースを新たに確保しながら、固定資産税がかからないことはロフトの大きな魅力といえるでしょう。
注意点として、天井高1.4m以下などの要件を満たさないとロフトは建築基準法における「小屋裏物置等」にはならず、固定資産税の課税対象面積に含まれます。
当然ながら固定資産税がかかり、節税効果は得られません。
なお、ロフトの要件は自治体によって異なる場合があるため、ロフトを設ける際は自治体の建築指導課や税務課などの担当窓口に問い合わせて要件の確認をおこなうことが重要です。
平屋がおしゃれになる
平屋にロフトを設けるとロフトがアクセントになり、平屋が一層おしゃれになります。
ロフトはよく秘密基地に例えられますが、一般の居室にはない独特の魅力と雰囲気があります。
ロフトは吹き抜けになっているため、開放的であることも魅力の一つです。
下階とロフトのデザインを調和させるのがポイントで、間取りとデザインを工夫するとさらにおしゃれになります。
平屋の全体的な魅力が向上するような設計アプローチが重要です。
ロフト付き平屋の設計や施工を得意としているハウスメーカーや設計事務所に依頼すると、おしゃれなデザインを考案してくれます。
設計を依頼する際は、外観も含めて自分の好みやイメージをしっかり伝えることが大切です。
平屋にロフトを設けるデメリット

ロフトは居室ではなく「小屋裏物置等」として扱われます。
したがって、一般の居室にはないデメリットが存在します。
ロフトを設ける際はメリットだけでなく、デメリットの考慮も必要です。
ここでは、平屋にロフトを設けるデメリットを解説します。
熱がこもりやすく暑い
ロフトは屋根の近くに位置するため、屋外の気温の影響を受けやすく、夏場は熱がこもって高温になりやすい特性があります。
ロフトを収納スペースではなく部屋として使用する際は、ロフト内にエアコンを設置するなどの暑さ対策が重要になってきます。
エアコンの設置は、ロフト内の温度を効率的に下げられるため、最も効果的な暑さ対策です。
ロフトの広さに合わせて、適切なサイズのエアコンを選びましょう。
ただし、自治体によっては、ロフトにエアコンの設置は禁止されていることがあるため注意が必要です。
断熱材を使用すると、屋外からの熱の侵入を防げます。
壁や天井に断熱材を施工することで、ロフト内の温度上昇を抑えられます。
また、ロフトの窓を開けたり換気扇を設置したりして、十分な通風を確保しましょう。
屋根の塗り替えや遮熱シートの設置なども、ロフトの暑さ対策として有効です。
コンセントやジャックに制限がある
ロフトは「小屋裏物置等」であり、コンセントは1ヵ所しか設置できません。
したがって、使用できる電化製品は限りがあります。
電源タップや延長コードを設置したり、ポータブル電源を設置したりなどの工夫が必要になるでしょう。
ただし、ロフトに設置する電化製品の合計消費電力が、契約している電力会社の契約アンペア数を超えないよう注意する必要があります。
詳細はハウスメーカーや電気工事業者などに相談してください。
また、ロフトにはテレビやインターネットなどのジャックは設置できません。
インターネットはWi-Fiを使用すると利用できますが、テレビを視聴するにはAmazon Fire TV Stickなどの映像出力デバイスを設置するといった工夫が必要です。
使用しなくなることがある
ロフトは暑くて天井が低いなどのデメリットがあるため、最初は使っていても徐々に使用しなくなり、無用の長物になる可能性があります。
将来も考えて、ロフトが本当に必要であるかを検討することが大切です。
ロフトは掃除がしにくいというデメリットもあり、固定階段を設置できない場合は可動式はしごを使っての上り下りになります。
可動式はしごは固定階段に比べて面倒なため、徐々に使わなくなることもあるでしょう。
ロフトはおしゃれでかっこいいと思っても短絡的に考えず、メリットとデメリットをバランス良く評価して判断すべきです。
平屋にロフトを設けるには費用がかかるため、建設コストを低く抑えたい方は慎重に検討しましょう。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
ロフト付き平屋の費用の目安

ロフト付き平屋の建設費用は、平屋の建設費+坪単価4~7万円が目安です。
ローコスト住宅であれば坪単価は30~50万円程度であり、これに坪単価4~7万円が上乗せされます。
例えば、坪単価が40万円のローコスト住宅の場合だと、ロフトを付けると坪単価は44~47万円になり、30坪だと建設費用は1,320~1,410万円になります。
この場合におけるロフトの設置費用は120~210万円です。
これはあくまでも建物のみの建設費用であり、土地代や付帯工事費、諸費用などが別途かかります。
床面積が同じであれば2階建てよりも割高になることがあるため、建設コストを低く抑えたい方はロフトの設置や増築は慎重に検討しましょう。
平屋にロフトを設ける際の注意点
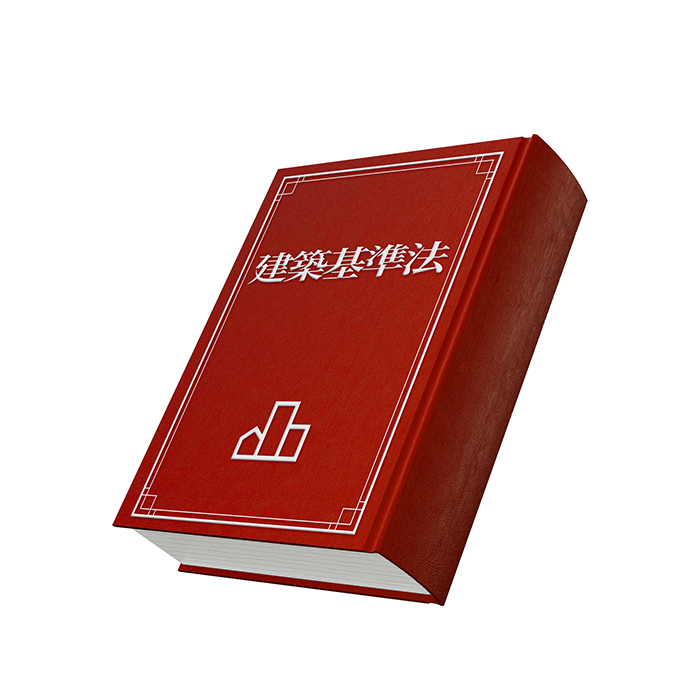
ロフトの設置は機能的でおしゃれな空間を作り出す素晴らしい方法である一方、適切な計画と設計が必要です。
特に建築基準法や自治体の決まりは遵守しなければなりません。
ここでは、平屋にロフトを設ける際の注意点を解説します。
天井の高さや床面積に制限がある
平屋にロフトを設置する際は、天井の高さや床面積に制限があります。
ロフトは天井高1.4m以下、床面積は下の階の2分の1未満にすることが必要です。
この制限を超えると通常の居室として扱われ、ロフトのスペースも床面積に参入されます。
天井高が1.4m以下だと大人は立ち上がれず、腰をかがめての移動になります。
1.4mを超える高さにするには居室としての扱いを受け、固定資産税の増額を負担しなければなりません。
ロフトが居室としての扱いを受けると2階建てになり、平屋ではなくなります。
なお、自治体によっては上記のほかにも独自の要件を定めている場合があります。
事前に必ず自治体が定める要件を確認することが大切です。
固定階段を設置できない場合がある
ロフトは基本的には、取り外し可能な可動式はしごで昇降するのが原則です。
しかし、自治体によっては固定階段の設置が認められている場合があります。
固定階段にすることで昇降が楽になり、重い荷物も運びやすくなります。
ロフトを子ども部屋にする場合も固定階段だと子どもは簡単に上り下りができるので安心です。
ただし、固定階段を設置すると1階に階段スペースを確保しなければならず、間取りが狭くなってしまいます。
間取りプランに影響が出るため、固定階段が設置できる場合でもよく検討して決めましょう。
なお、固定階段にできるかどうかは自治体の建築指導課での確認が必要です。
事前に必ず確認するようにしてください。
落下事故を防ぐための安全対策が必要
平屋にロフトを設置する際は、転落事故を防止するための安全対策が必要です。
ロフトを子ども部屋にしたり、寝室にしたりする際は特に注意を要します。
ロフトは天井付近の高所に設置するため、転落すると大怪我をする可能性があります。
安全対策として、格子やロープネット、手すりなどの設置が必要です。
設置が可能であれば固定階段が望ましく、可動式はしごを使用する際は安全で適切な設計であることを確認しましょう。
屋根裏のロフトは暗いため、段差や障害物で転倒することがあります。
ロフト内に明るい照明を設置して、段差や障害物を見つけられるようにすることも大切です。
照明は明るく消費電力が少ないLEDライトをおすすめします。
ロフト付き平屋の間取り例
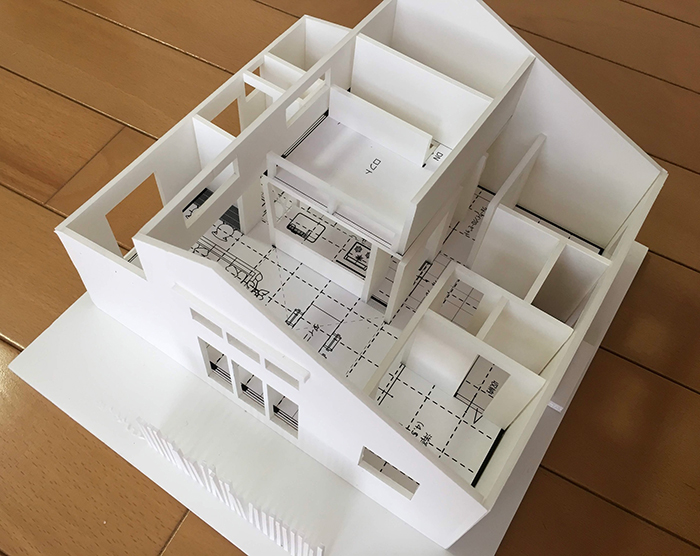
ロフト付き平屋の間取り図や実例は、ハウスメーカーや工務店などのホームページやブログで紹介されています。
さまざまな間取りを確認することは住宅建設において重要です。
ここでは、ロフト付き平屋の間取り例をご紹介します。
ロフトを子ども部屋にする際の間取り例
ロフトを子ども部屋にする際の間取り例として、LDKを1階の中央に設置し、周辺に居室を配置する間取りが挙げられます。
どの居室からもLDKに楽に移動でき、生活動線や家事動線がスムーズになります。間取りを設計する際は、動線の意識が重要です。
ロフトはLDKから見渡せる場所に設置し、子ども部屋として使用します。
この間取りならLDKからロフトを見渡せるため、家事をしながらでも子どもの様子を見守れて便利です。
LDKを中央に配置する間取りは、家族のコミュニケーションの促進に役立ちます。
ロフトの子ども部屋の様子も確認しやすく、安全性も向上します。
また、ロフト内には子どもの年齢や好みに合った設備や収納スペースの設置も検討しましょう。
ロフトを趣味の部屋にする際の間取り例
玄関ホールの正面にLDKを配置し、LDKの右側と左側に居室を配置する間取りは、家族のプライバシーを確保できます。
小さな子どもがいる家庭には向きませんが、大人が気兼ねなくプライベートな時間を過ごしたい場合には最適でしょう。
ロフトは固定階段を設置して、玄関ホールから昇降できるようにします。
帰宅すると玄関からすぐにロフトにアクセスできる仕組みです。
このような間取りは、ロフトを大人の趣味の部屋にするのに適します。
ロフトを趣味の部屋にする際は、畳を敷いて和室にするなどのアイデアを反映させましょう。
ロフトをあえて広くせず、狭い空間にすると大人の秘密基地や隠れ家のような雰囲気になります。
狭い空間は集中力が増すため、仕事部屋や勉強部屋にも適します。
ロフトを収納スペースにする際の間取り例
ロフトを収納スペースにする際の間取り例として、玄関ホールの正面にLDKを配置し、LDKの左側に居室を配置する間取りが挙げられます。
ロフトには固定階段を設置して、LDKから昇降できるようにします。
このような間取りは家族と適度なコミュニケーションを取りながら、各人のプライバシーを確保するのに最適です。
玄関から入って自分の部屋に行くには必ずLDKを通る必要があります。
親はLDKで家事をしながら、帰宅してきた子どもと会話ができます。
LDKから固定階段でロフトの収納スペースにアクセスできるため、荷物の出し入れも楽です。
ロフトは可能な限り広いスペースを確保すると大量の荷物を収納でき、平屋をより広く使えます。
まとめ

平屋にロフトを設けると屋根裏のデッドスペースの有効活用が図れ、固定資産税の節税効果も得られます。
平屋が一層おしゃれになり、趣味の部屋やテレワークの仕事部屋などに活用できます。
しかし、天井高1.4m以下などの要件を満たさないと居室として扱われ、節税効果は得られません。
床面積が同じであれば2階建てよりも割高になることもあるため、お金をかけてまでロフトを設ける必要があるのかを見極めましょう。
平屋の物件をお探しの方へ
ちゅうこだて!はロフト付きの平屋など様々な中古一戸建ての情報をご紹介しています。
新築よりもお得にロフト付き平屋を購入したい方は、ぜひチェックして、お目当ての物件を探してみてはいかがでしょうか。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
The post 平屋にロフトを設けるメリット・デメリットとは?間取り例と注意点を解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>The post コの字型平屋のデメリットとは?|デメリットの解決策とメリットを解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>コの字型の平屋はカタカナのコの字の形をしていて、建物の一部が凹んでいるのが特徴です。
凹んだ部分には開放的な中庭があり、日当たりや風通しの良さを感じられます。
しかし複雑な形状であるため、デメリットも理解したうえで選ぶことが重要です。
この記事ではコの字型平屋のデメリットと解決策、メリットを解説します。
コの字型以外の平屋の種類も解説するため、それぞれの特徴を比較して最適な平屋を選んでください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
コの字型平屋のデメリットと解決策

コの字型平屋は複雑な形状をしていることから、以下のデメリットが懸念されます。
- デメリット①建築コストが高い
- デメリット②動線が長くなる
- デメリット③維持管理に手間がかかる
- デメリット④プライバシーを確保しにくい
デメリットを回避するためには、適切な解決策を知っておくと安心です。
それぞれのデメリットと解決策を解説します。
デメリット①建築コストが高い
建物の形状が複雑になるほど、施工に手間がかかり建築コストは高くなります。
コの字型平屋は凹凸や継ぎ目が多いため、建築コストが高額になりやすいです。
建築会社によって差がありますが、コの字型平屋は通常の平屋よりも1坪あたり2〜5万円程度価格が高くなることが多いといわれています。
中庭の外構工事も、コストアップの原因になります。
中庭は平屋の中心部分に位置するため、美しく見せるために植栽や照明、ウッドデッキにこだわる方は多いです。
開放的な雰囲気を演出する目的で中庭側の窓を増やす場合も、サッシの材料費が高くつきます。
さらにコの字型平屋を建てるためには広い土地を確保しなければなりません。
建築コストだけでなく土地代も高ければ、トータルで莫大な出費になります。
建築コストを抑えるための解決策は、できるだけシンプルに仕上げることです。
複雑な形状よりシンプルな形状のほうが、建築コストを安く抑えられます。
途中で予算オーバーにならないよう、事前に予算を決めてから設計を相談することもポイントです。
デメリット②動線が長くなる
コの字型平屋は動線が長くなる点がデメリットです。
直線が折れ曲がったような形状をしているため、端から端に移動するのに時間がかかります。
頻繁に行き来する部屋同士が離れていると、使い勝手が悪いです。
中庭を横切れば、離れている部屋にショートカットできますが、段差の上り下りや靴の脱ぎ履きが面倒な方も多いでしょう。
雨が降っていると家の敷地内で傘をささなければならず、とても不便です。
動線計画を組む際は、室内を通る前提で考えましょう。
解決策としては、中央部分にLDKや水回りなどをまとめる方法が有効です。
LDKは家のなかで過ごす時間が長い空間で、家族が集まる共有スペースでもあるため、中央部分に配置することで動線を短縮できます。
LDKの近くに水回りがあると、家事効率アップにもつながります。
コの字型平屋で使い勝手の良い動線計画を考えるのは、難易度が高い作業です。
設計を依頼する際は、コの字型平屋の実績が豊富な建築会社を選ぶことをおすすめします。
デメリット③維持管理に手間がかかる
維持管理に手間がかかるデメリットもあります。
特に維持管理が大変な場所は中庭です。
コの字型平屋は中庭との一体感が魅力であるため、こまめに維持管理をしないと見栄えが悪くなってしまいます。
雑草が伸びる時期には、草むしりも欠かせません。
中庭側の窓が汚れている場合は、窓掃除も必要です。
三方向が壁で囲まれているコの字型平屋の中庭は、水はけが悪くなる可能性もあります。
ジメジメとした空気にならないよう、水をためないことがポイントです。
排水溝に枯れ葉やゴミなどが詰まってしまうと、中庭に水がたまる原因になります。
維持管理の手間を減らすためには、適切な排水対策が不可欠です。
例えば中庭に大きめの砂利を敷くことで、水はけが良くなります。
コンクリートなど水はけが悪い素材を中庭に使う場合は、しっかりとした雨水経路を確保することが肝心です。
ウッドデッキを設ける場合は定期的にメンテナンスをおこないます。
劣化や変色が見られる場合は、費用をかけて修繕しなければなりません。
樹脂タイプのウッドデッキであれば、劣化しにくく、美しい見た目を長期間維持できます。
デメリット④プライバシーを確保しにくい
建物の向きによっては、道路からの視線が気になる場合があります。
中庭部分が道路側に向いていると、家のなかが丸見えになってしまうことも多いです。
平屋は通行人と視線の高さが同じであるため、プライバシーには特に配慮が必要になります。
隣の建物から家のなかが見えないかどうかも、確認しておきたいところです。
覗いているつもりはなくても、お互いに目があってしまうと気まずい思いをします。
せっかくのプライベート空間なのに、思う存分くつろげません。
都市部の場合は隣の家だけでなく、近隣のマンションなど高層建築物からの視線もチェックしましょう。
プライバシーを確保するための解決策は、道路側にカーテンや柵など目隠しを建てることです。
しっかりと目隠しができれば、道路からの視線をカットしたプライベートな中庭がつくれます。
目隠しの素材をフェンスやルーバー、植栽などにすれば、圧迫感も少ないです。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
コの字型平屋のメリット

中庭があるコの字型平屋では、快適な暮らしが叶います。
コの字型平屋のメリットは以下のとおりです。
- メリット①日当たり・風通しが良い
- メリット②中庭を多目的に活用できる
- メリット③おしゃれな外観になる
- メリット④二世帯住宅にも向いている
メリット①日当たり・風通しが良い
コの字型平屋は建物の表面積が広いため、長方形の平屋よりも多くの窓を設置できます。
大きな窓を並べれば、室内に日光を取り入れやすいです。
一般的な平屋では中心部分や北側部分の日当たりが悪くなることが多いですが、コの字型にすることで平屋の弱点を解消できます。
風通しが良い点も、コの字型平屋のメリットです。
一部屋に二カ所以上の窓を設けると、空気が循環しやすく風通しが良くなります。
常に新鮮な空気を取り入れられるため、室内で過ごすときの快適性が向上します。
日当たりが良い家にするためには、コの字型の方角を考慮しなければなりません。
日当たりが良いのは南向きですが、その他のチェックポイントもあります。
例えば「西日がまぶしくないか」「近隣の高層建築物によって日光が遮られていないか」といった点も忘れずにチェックしましょう。
メリット②中庭を多目的に活用できる
中庭を多目的に活用できる点も、コの字型平屋のメリットです。
中庭の利用目的は多岐にわたりますが、例えば以下のような利用目的が挙げられます。
- 子どもの遊び場
- 車や自転車の駐車スペース
- 物干しスペース
- バーベキュー
- 坪庭
- ガーデニング
小さな子どもがいる世帯にとって、中庭は安全な遊び場になります。
親はリビングやキッチンから子どもが遊んでいる姿を見守りやすく、何かあったときもすぐに対応できて安心です。
道路への飛び出しや不審者との接触も防げます。
最初から特定の利用目的を決める必要はなく、フリースペースとして中庭を確保しておくのも手です。
一人で過ごすくつろぎ時間から、家族で過ごす賑やかな時間まで、あらゆるシーンで活躍するでしょう。
メリット③おしゃれな外観になる
コの字型平屋は個性的でおしゃれな外観を演出できます。
長方形の平屋はよく見かけますが、コの字型平屋は比較的珍しいデザインです。
ほかの家とは違う、周囲から一目置かれる存在になることでしょう。
ほかの家と差別化を図りたい方にぴったりです。
コの字型平屋ならではの日当たりの良さやプライベート感を活かして、中庭をリゾートライクな雰囲気に仕上げることもできます。
木の質感や中庭の一体感を活かした、和モダンなデザインとも相性が良いです。
デザインのテイストに関わらず、コの字型平屋のゆったりとした佇まいは高級感が漂います。
メリット④二世帯住宅にも向いている
コの字型平屋は二世帯住宅にも向いています。
間取りは中央部分をリビング、両サイドを各世帯の居住スペースにするのがおすすめです。
コの字型平屋は動線が長くなるのがデメリットですが、二世帯住宅であれば動線の長さを活かして各世帯の距離感を確保できます。
お互いのプライバシーを守りつつ、ほどよくコミュニケーションをとれるのが魅力です。
上下階で世帯を分けている二階建ての二世帯住宅では、生活リズムの違いによってお互いの生活音がうるさいと感じることがあります。
しかしコの字型平屋であれば、中庭を挟んでいるため生活音はあまり気になりません。
中庭を共有スペースにすることで、世帯間のコミュニケーションもとりやすいです。
週末は中庭で一緒に食事をしたり孫と遊んだり、一緒に過ごすきっかけがつくれます。
コの字型以外の平屋の種類
平屋の形状は、コの字型以外にもI字型、L字型、ロの字型があります。
それぞれのメリット・デメリットをまとめました。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| I字型 | ・建築コストが安い ・大空間をつくりやすい ・間取りの自由度が高い |
・音が響きやすい ・日当たりが悪い ・プライベートな空間を確保しにくい |
| L字型 | ・プライベートな空間を確保しやすい ・日当たりが良い ・変形地を有効活用できる |
・建築コストが高い ・維持管理に手間がかかる ・防犯対策が必要 |
| ロの字型 | ・中庭のプライバシーが高い ・日当たりが良い |
・広い土地が必要 ・中庭の水はけが悪い |
I字型
I字型平屋は、一方向に伸びた長方形の形状です。
シンプルな形状であるため、凹凸や継ぎ目を最小限に抑えられるのが特徴です。
コの字型平屋のように壁に囲まれたプライベートな中庭はつくれませんが、建物の周りにオープンな庭をつくれます。
最大のメリットは壁が少ないシンプルな形状であることです。
凹凸や過ぎ目が少なくて済むため、建築コストを安く抑えられます。
柱や壁の数を減らした大空間もつくりやすく、開放的なLDKを実現できるでしょう。
間取り設計の自由度が高く動線もコンパクトにまとめられるため、住んでからの使い勝手も良い形状です。
動線が短いのは便利ですが、家中に音が響きやすいというデメリットもあります。
水回りの音は特に響きやすく、各部屋との位置関係に注意が必要です。
部屋同士が隣り合っているため、完全にプライベートな空間を確保することも難しいです。
また中心部分や北側部分は日当たりが悪くなることが多いため、暗い雰囲気になってしまう恐れがあります。
L字型
L字型平屋とは、建物がアルファベットのLの形をしています。
中庭に向かって縦と横に二辺で構成されている構造です。
L字型の向きは道路側に開けているタイプと、敷地の奥に開けているタイプがあります。
L字型平屋はゾーン分けしやすいというメリットがあります。
縦と横の二辺を人が集まる空間とプライベートな空間の二つのゾーンに分けられます。
L字の内側にある中庭は、外からの視線をカットしながら、日当たりの良さや開放的な眺望が手に入る点もメリットです。
三角形や細長い形など変形地であっても、L字の長辺を調節することで土地を有効活用できます。
一方で建築コストが高くなる点がデメリットです。
I字型平屋と比べると、壁や屋根の面積が増えるため、建築コストは高額になります。
また外に接する面が多いことから外気の影響を受けやすく、光熱費も高くなる傾向です。
また建物の入隅部分は強度が弱いため、メンテナンスや補強をおこなわなければなりません。
さらにL字型平屋は外部から不審者が侵入しやすい構造のため、十分な防犯対策が必要です。
ロの字型
ロの字型平屋はカタカナのロの形をした住宅です。
コの字型住宅の壁を一辺追加して、中庭が閉じている形状を想像していただくとわかりやすいでしょう。
中庭が外部に面していないため、プライバシーが確保されています。
ロの字型平屋のメリットは、外からの視線を気にせずプライベートな空間を楽しめることです。
ゆっくり読書をしたり洗濯物を干したり気兼ねなく活用できるでしょう。
家のなかからは中庭が見えるため、眺望に閉塞感はありません。
中庭から降り注ぐ日光が、室内に優しい光を届けてくれます。
一方でデメリットは広い土地が必要になることです。
中央部分に中庭をつくり、それを囲む建物をつくるには、ある程度まとまった土地でなければ成立しません。
また中庭の水はけが悪いことも注意点です。
雨水が中庭にたまると、ジメジメとした空気が発生し家が傷む原因にもなります。
しっかりとした排水対策を計画しましょう。
まとめ

コの字型平屋は近年注目されていますが、建築コストや維持管理のデメリットを認識しておかなければなりません。
デメリットを補うための解決策を知っておくことも大切です。
しっかりと対策をすれば、プライベートな中庭を活用しながら豊かな暮らしができます。
平屋の物件をお探しの方へ
ちゅうこだて!は中古一戸建ての物件情報を検索できるサイトです。
この記事でご紹介したようなコの字型の平屋など、お目当ての物件をちゅうこだて!で探してみてはいかがでしょうか。
市区町村や最寄り駅など条件を絞って物件情報を探せるため、中古一戸建ての購入を検討している方はぜひ活用ください。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
The post コの字型平屋のデメリットとは?|デメリットの解決策とメリットを解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>The post スキップフロアがある平屋のメリット・デメリット|活用例や後悔しないポイントも解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>スキップフロアは一階しかない平屋の空間を有効活用できる方法の一つです。
もともと平屋は高齢世帯から選ばれていましたが、近年は若い世帯の間でも平屋の人気が高まっています。
新型コロナウイルス感染拡大によってリモートワークが普及し、郊外の広い土地に平屋を建てる世帯が増えたことが一因と考えられます。
平屋にスキップフロアを設ける際は、将来を見据えた間取り設計が欠かせません。
この記事ではスキップフロアがある平屋のメリット・デメリットを解説します。
スキップフロアの活用例や後悔しないポイントもまとめました。
\ 平屋の中古物件を探したい /
スキップフロアとは

スキップフロアとは、同じフロアのなかに異なる高さの空間が設けられた間取りです。
例えばフロアを一段上げたり下げたりするだけでもスキップフロアと呼びます。
フロアの高さは階段一段分の小さな段差から中二階のような大きな段差までさまざまです。
高さが違うフロアがゆるやかにつながることによって、立体的な空間になります。
スキップフロアは平屋だけでなく、二階建てや三階建ての一戸建てで採用されることも多いです。
スキップフロアと似たような言葉としてロフトがあります。
ロフトは建築基準法に定められた空間で、「1.4m以下の高さ」かつ「下階の50%未満の面積」などスキップフロアに比べて条件が明確です。
条件を満たす場合は、建物の延べ床面積から除外され、固定資産税の課税対象面積からも除外されます。
スキップフロアがある平屋のメリット

スキップフロアのある平屋は、空間に変化をつけておしゃれに仕上げられる点が大きなメリットです。
具体的には、以下のメリットがあります。
- メリット①縦の空間を有効活用できる
- メリット②採光を確保しやすい
- メリット③開放感を演出できる
メリット①縦の空間を有効活用できる
スキップフロアがあると縦の空間を有効活用できるため、一階しかない平屋でも広々とした印象になります。
通常の平屋は一階部分のみに限定され、横の空間しか活用できません。
横の空間を仕切るための壁や扉が増えてしまい、圧迫感のある印象になってしまいます。
しかしスキップフロアはフロアの高さの違いによって空間を仕切るため、圧迫感が少ないです。
また、土地面積が狭くても限られた空間を有効活用できるスキップフロアは、狭小地と相性が良いです。
狭小地で平屋を建てようとすると家のなかが窮屈になりがちですが、スキップフロアで縦の空間を増やせば広く見せられます。
特に都心部は空いている土地が少なく、狭小地しか選択できないことも多いです。
二階建てや三階建てのように建物自体の高さを変えずに済むため、高さ制限がある地域で平屋を建てる場合にも適しています。
メリット②採光を確保しやすい
スキップフロアのある平屋は採光を確保しやすく、日当たりが良い点もメリットです。
通常の平屋では壁や扉によって、窓からの光が遮られてしまいます。
そのため平屋の中心部分や北側部分など、建物の奥のほうが暗くなることが多いです。
しかしスキップフロアであれば壁や扉などの遮へい物を減らせるため、室内の奥まで光が入りやすく、どこにいても明るい空間で過ごせます。
日当たりを重視する方は、方角に合わせて段差の取り方や窓の位置を決めましょう。
例えば南向きの窓はできるだけ高い位置に設置するのがおすすめです。
フロアとフロアの間に窓を設けて、採光を確保する方法もあります。
適切な位置に窓を設置すると、採光だけでなく風通しも良くなるでしょう。
メリット③開放感を演出できる
平屋に立体的なスキップフロアをつくることで、開放感が生まれるというメリットもあります。
横の仕切りを抑えられるため、空間が細切れになりません。
異なる用途の空間がゆるやかなつながりを持ち、一つの大きな空間をつくりだします。
開放感が生まれることによって、家族同士のコミュニケーションも増えるでしょう。
違う部屋で過ごしていても、お互いの存在を感じられます。
スキップフロアはほかとは違う個性的な雰囲気を演出できるため、「おしゃれな家に住みたい」という方にも人気です。
スキップフロアによって単調な平屋の雰囲気はがらりと変わり、空間全体にアクセントが生まれます。
高さの変化を活かして、リゾートホテルのような雰囲気も演出できるでしょう。
スキップフロアがある平屋のデメリット

スキップフロアはメリットばかりではありません。
スキップフロアのある平屋を検討する際は、以下のデメリットを意識しましょう。
- デメリット①建築コストや固定資産税が高い
- デメリット②段差が生まれる
- デメリット③空調管理が難しい
デメリット①建築コストや固定資産税が高い
平屋の快適性向上が期待できるスキップフロアですが、経済面においてはデメリットがあります。
経済的な負担が大きくなりやすいのが、建築コストや固定資産税です。
スキップフロアのある平屋を新築する場合、階段や床を追加して新たな空間をつくるため建築コストが高くなります。
材料が増えたり手間がかかったりするため、材料費や人件費がアップすることが原因です。
通常の平屋を想定して予算を組んでいると、大きく予算オーバーしてしまうケースも少なくありません。
スキップフロアによって住宅の床面積が増えた場合は、固定資産税も上乗せされます。
固定資産税は毎年納めなければならないため、平屋を購入したあともランニングコストの負担が増える点に注意しましょう。
デメリット②段差が生まれる
スキップフロアでは段差が生まれるため、バリアフリーの面ではデメリットです。
老後を見据えて平屋を選んでいる方は、スキップフロアによって平屋のメリットを打ち消してしまうことになりかねません。
若いときに住むのは特に問題ないですが、年齢を重ねたときにスキップフロアの段差を不便に感じることが多いです。
小さい子どもがいる場合も、段差でつまずいてケガをしてしまう可能性があります。
ホームエレベーターを取り入れれば段差は解消されますが、建築コストがかかるうえに間取りが制限されてしまいます。
段差の近くには手すりを付けておく、キッチンやリビングなどのスペースは平面に収めるなど、予算に合った適切な対策が不可欠です。
デメリット③空調管理が難しい
空調が効きにくく温度管理が難しい点も、スキップフロアのデメリットです。
スキップフロアを設置すると上の段に合わせて天井が高くなります。
さらに部屋を仕切る壁が少なく、室内全体が広いワンルームのような状態です。
大空間では効率良く空調管理ができないため、夏は暑く冬は寒くなります。
大容量の空調設備を設置する方法が有効ですが、消費電力が増える分、毎月の光熱費が高額になる点は覚悟しなければなりません。
音やにおいが漏れやすい点にも注意が必要です。
例えばキッチンで調理すると油を含んだ空気が充満し、家具を汚す可能性があります。
リビングでの会話が書斎まで筒抜けになってしまい、仕事に集中できない可能性もあるでしょう。
平屋におけるスキップフロア活用例

平屋のスキップフロアにはさまざまな活用例があります。主な活用例は以下のとおりです。
- 来客用の寝室
- 子ども部屋
- 書斎
- セカンドリビング
- 収納
来客用の寝室
平屋のスキップフロアを来客用の寝室として活用する方法です。
いつもは使用しませんが、子どもの家族が泊まりに来たときなどに活躍します。
家族同士であれば、ほど良いつながりを感じながら過ごせる点もメリットです。
スキップフロアに来客用の寝室を設ければ、一階部分に客間をつくる必要がありません。
普段の生活は段差のない一階部分で完結するため、老後も安心して生活できるでしょう。
ただしスキップフロアは壁や扉が少ないため、プライバシーを確保しにくい点に注意しなければなりません。
ゲストによっては十分に寛げない可能性があります。
家族や親しい友人など気心が知れたゲストが使う寝室として使用しましょう。
子ども部屋
スキップフロアを子ども部屋として活用する方法もあり、子育て世帯に人気です。
平屋の場合面積が限られているため、たくさんの部屋はつくれません。
子ども部屋を確保する余裕がない場合、スキップフロアを子ども部屋として活用するのがおすすめです。
スキップフロアを見渡せる間取りであれば、リビング・キッチンで家事をしながら子どもを見守れます。
親の目が届きやすく、必要なときにコミュニケーションをとれる点が魅力です。
ただし子どもは成長するにつれて、プライベートな子ども部屋を求める傾向があります。
将来を見据えて、スキップフロアとは別に子ども部屋を確保しておくと安心です。
人数分の子ども部屋をつくるのが難しい場合は、広い部屋を可動式の壁で仕切る方法があります。
書斎
スキップフロアは書斎としても活用できます。読書や手芸など、書斎の使い方は多種多様です。
デスクセットやインターネット環境を整えれば、リモートワークの仕事場にもなります。
コロナ禍以降、家で仕事をすることが増えたという方は多いのではないでしょうか。
スキップフロアの書斎は、仕事をしながら家族を見守りたい方に最適です。
一方で集中したい方にとっては、ほかの部屋の音が作業の邪魔になる可能性があります。
例えば書斎の横にリビングや子ども部屋があると、音が気になって集中できません。
オンラインの打ち合わせや集中して作業をしたい場合は、書斎とほかの部屋の位置関係に気を付けましょう。
セカンドリビング
スキップフロアをセカンドリビングとして活用する方も多いです。セカンドリビングとは、メインリビングとは別の二番目のリビングです。
もともとセカンドリビングは二世帯住宅で取り入れられることが多かったのですが、最近は一世帯で暮らす住宅でも注目されています。
セカンドリビングの使い方は、メインリビングの横に畳敷きの小上がりスペースを設けたり、階段を上った先にピアノを置いたりする活用例があります。
床の高さを変えるだけで「家族が集まるメインリビング」と「一人で寛げるセカンドリビング」のようにゆるやかな仕切りが生まれる仕組みです。
収納
収納スペースが不足している場合は、スキップフロアを収納スペースとして活用するのがおすすめです。
平屋では生活の必須スペースを設けるのが精一杯で、十分な収納スペースを設けられないことがあります。
厚手のコートや扇風機など季節限定で必要なものは意外と多いです。
子どものおもちゃ・本の置き場所に悩んでいる方も多いでしょう。
このように普段は使わないものをスキップフロアに収納できると、居住空間がすっきりします。
背の低い収納スペースであれば、スキップフロアの下にあるデッドスペースも有効活用できます。
掃除家電や消耗品のストックを収納しておくと便利でしょう。
また、収納のみの目的であれば、スキップフロアではなくロフトを検討してみてはいかがでしょうか。
建築基準法の条件を満たせば、固定資産税を減らせる可能性があります。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
平屋のスキップフロアで後悔しないポイント

平屋のスキップフロアで後悔しないポイントは以下のとおりです。
- スキップフロアの利用目的を決める
- 老後の暮らしを見据えた間取りにする
- 断熱性を高める
スキップフロアの利用目的を決める
明確な利用目的がないまま平屋にスキップフロアをつくるのは後悔のもとです。
時間が経つにつれて使われなくなり、無駄なスペースになってしまう可能性があります。
スキップフロアを設置する際は、最初に利用目的を考えましょう。
また、利用目的を考えるときは、一人で決めるのではなく、家族で話し合うことが大切です。
利用目的が決まったら、ほかの部屋との相性も考えなければなりません。
スキップフロアの利用目的を書斎と決まれば、子ども部屋とは離すなど、あらかじめ間取りの配置を工夫できます。
長期的な視点で利用目的を考えることも、後悔しないポイントです。
子どもが小さいうちはスキップフロアを子ども部屋として使い、独立したあとは来客用寝室にするなど、将来のイメージも膨らませておきましょう。
老後の暮らしを見据えた間取りにする
「若いときにスキップフロアをつくったものの、年を取ってから使いづらい」という後悔の声は多く聞かれます。
ずっと快適に暮らしていくためには、老後のライフスタイルを見据えてスキップフロアを計画することが肝心です。
リビングやキッチンなどの機能をスキップフロアにつくってしまうと、毎日階段の上り下りをしなければならず足腰の負担が大きいです。
最悪の場合、段差から転倒してしまうなど、深刻な事故につながる危険性もあります。
生活の必須スペースは、できるだけ段差のない一階部分で完結させましょう。
スキップフロアは使用頻度の少ない収納や来客用客室として使用するのがおすすめです。
スキップフロア以外の部分は車椅子が使えるように段差をなくす、手すりを設置するなど、バリアフリー機能を整えておきます。
断熱性を高める
スキップフロアがある平屋は、空調が効きにくく光熱費が高くなるのが難点です。
部屋全体を快適な温度に保つためには、断熱性を高める必要があります。
断熱性が高い平屋にすれば、スキップフロアのある広い空間であっても、快適な室温を長時間キープしやすいです。
具体的な方法は外壁やサッシに断熱性の高い素材を使用することや、窓の位置を工夫することです。
断熱性に優れた素材は数多く登場しているため、性能と価格のバランスが良いものを選びましょう。
平屋全体の空調を一括で管理できる全館空調を活用するのも手です。
全館空調は小屋裏に大型の空調設備を設置して、空調を管理する仕組みです。
導入コストがかかりますが、室内の温度差が少なくなり、ヒートショックや熱中症のリスクを防止できます。
まとめ

スキップフロアがある平屋は縦の空間を有効活用でき、日当たりが良く開放的な雰囲気を演出できるのがメリットです。
スキップフロアの使い方はさまざまですが、来客用の寝室や書斎など使用頻度が少ない部屋として活用すれば、老後の生活にも支障が出ません。
平屋の物件をお探しの方へ
ちゅうこだて!は中古一戸建ての物件情報を検索できるサイトです。
この記事でご紹介したようなスキップフロアがある平屋など、ちゅうこだて!でお目当ての物件を探してみてはいかがでしょうか。
市区町村や最寄り駅など条件を絞って物件情報を探せるため、中古一戸建ての購入を検討している方はぜひ活用ください。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
The post スキップフロアがある平屋のメリット・デメリット|活用例や後悔しないポイントも解説 first appeared on ちゅうこだて!コラム.
]]>