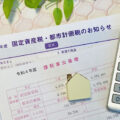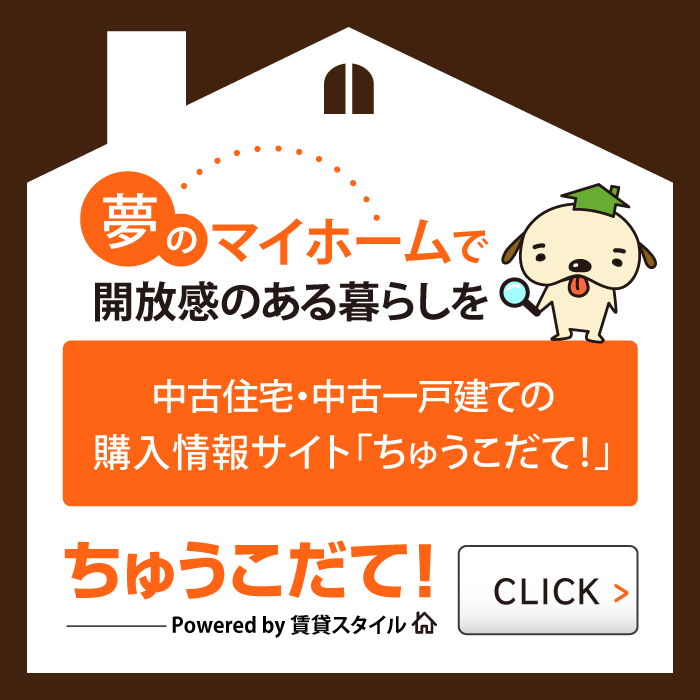「30坪の平屋の固定資産税はいくらかかるのだろう」とお悩みではありませんか。
毎年納めなければならない固定資産税は、資金計画を組むうえでしっかりと把握しておきたいコストです。
この記事では30坪の平屋の固定資産税をシミュレーションし、二階建ての固定資産税と比較します。
平屋を探している方に向けて、固定資産税を安く抑えやすい平屋の特徴もまとめました。
\ 平屋の中古物件を探したい /
固定資産税とは

固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している方が納める税金です。
固定資産が所在する市町村に市町村税として納税するのが原則です。
ただし、東京都23区の場合は都税として東京都に納めます。
固定資産税額は毎年一律ではありません。
固定資産の評価は変動するため、3年に一度見直されます。
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に対して課税される仕組みです。
年の途中で固定資産を売買した場合は、所有している期間に応じて売り主と買い主でそれぞれ負担するのが慣例となっています。
固定資産税はどうやって決まる?
固定資産税の額は、市町村の長が固定資産評価基準に基づいて決定します。
新築平屋に入居してから固定資産税が決定されるまでの流れは以下のとおりです。
- 家屋調査
- 課税標準額(評価額)の決定
- 固定資産税の決定
- 納税通知書の交付
新築平屋の場合、入居してから1〜3ヵ月頃に家屋調査の連絡が入ります。
家屋調査では固定資産評価員が対象となる固定資産の評価をおこないます。
所要時間は30分程度で、図面などを用意しておくとスムーズです。
家屋調査などの結果を踏まえて、課税標準額(評価額)が決定します。
課税標準額(評価額)とは固定資産税額の計算する基礎となる値です。
課税標準額(評価額)をもとに計算された固定資産税が納税通知書に記載され、所有者に交付される流れです。
納期は市町村によって異なりますが、原則は年4回に分けて納税します。
固定資産税の計算方法
固定資産税の計算式は、以下のとおりです。
固定資産税=課税標準額(評価額)×1.4%(標準税率)
課税標準額(評価額)に対して、税率をかけて計算します。
設定されている税率は多くの場合、標準税率の1.4%です。
課税標準額(評価額)は市町村が決定した値であり、それぞれ以下の方法で算出されます。
| 土地の課税標準額(評価額) | 土地の面積×路線価 |
|---|---|
| 建物の課税標準額(評価額) | 評点一点あたりの価額×床面積×単位面積あたりの再建築費評点×経年減点補正率 |
中古平屋の場合、所有者に交付される課税明細書を確認すれば、過去の固定資産税の額がわかります。
固定資産評価証明書、公租公課証明書、固定資産税台帳にも記載されています。
過去の税額を知りたい場合は、仲介業者経由で売り主に固定資産税額を聞きましょう。
一方で新築平屋の場合は、入居後しばらくしないと固定資産税額の基礎となる課税標準額(評価額)が決定しません。
ただし、おおまかな金額であれば簡易的な計算方法で予測できます。
建物の課税標準額(評価額)は再調達原価の5~6割、土地の課税標準額(評価額)は公示価格の7割程度として計算します。
再調達原価とは、その建物を再び建てたときにかかる費用の目安です。
公示価格は国が算定する地価公示価格を参照します。
平屋の固定資産税の軽減措置

平屋の固定資産税には、以下の軽減措置があります。
- 新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置
- 住宅用地の課税標準の特例
新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置
新築住宅の床面積120㎡以下の部分まで、建物にかかる固定資産税が1/2に減額される措置です。
軽減措置を受けるためには、居住部分の割合が1/2以上、居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下といった条件を満たさなければなりません。
土砂災害特別警戒区域に建てられた新築住宅は適用対象外となります。
なお、軽減措置の適用期限は2024年3月31日までです。
軽減措置の適用を受ける場合は、市町村に固定資産税減額申告書(新築住宅)を提出する必要があります。
新築住宅の一戸建ては軽減期間が3年間ですが、長期優良住宅の一戸建ては5年間に延長されます。
長期優良住宅とは、耐震性・耐久性・可変性が高く長く住み続けられる住宅として、都道府県や市町村など所管行政庁に認定された住宅です。
新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置は、軽減期間を過ぎると固定資産税額がもとに戻るため、あくまで一時的な軽減措置ととらえておきましょう。
住宅用地の課税標準の特例
住宅の敷地として利用されている住宅用地では、土地の固定資産税に対して軽減措置が受けられます。
住宅用地の課税標準の特例は、小規模住宅用地の特例と一般住宅用地の特例があり、それぞれ軽減率が異なります。
小規模住宅用地の特例は200㎡以下の部分が対象で、軽減率は1/6です。
一般住宅用地の特例は200㎡を超える部分が対象で、軽減率は1/3となっています。
| 小規模住宅用地の特例(200㎡以下の部分) | 課税標準額が1/6に軽減 |
|---|---|
| 一般住宅用地の特例(200㎡超の部分) | 課税標準額が1/3に軽減 |
住宅用地の課税標準の特例は、適用期限が設定されていません。
住宅用地の課税標準の特例を申請する場合は、固定資産税住宅用地等申告書を市町村に提出します。
空き家になった土地も、原則として住宅用地の課税標準の特例は適用されます。
ただし特定空き家に指定され、勧告を受けた場合は適用対象外です。
また、建物の用途が住宅ではなくなったり、建物を解体したりした場合も適用対象外となるため注意しましょう。
平屋と二階建ての固定資産税を比較

平屋と二階建ての固定資産税はどちらが高いのでしょうか。
建物面積30坪の新築平屋と新築二階建てを建てた場合の固定資産税をシミュレーションしたところ、以下のような結果になりました。
| 新築平屋 | 新築二階建て | |
|---|---|---|
| 土地の固定資産税 | 7万円 | 3.5万円 |
| 建物の固定資産税 | 10.5万円 | 8.4万円 |
| 土地+建物の固定資産税 | 17.5万円 | 11.9万円 |
30坪の新築平屋の固定資産税シミュレーション
30坪の新築平屋の固定資産税を以下の条件でシミュレーションします。
築年数:新築
構造:木造一階建て
建ぺい率:50%
容積率:100%
建物面積:30坪(99㎡)
土地面積:60坪(198㎡)
土地単価:50万円/坪
土地評価額:3,000万円
建物評価額:1,500万円
まず土地の固定資産税を計算します。
平屋の場合は建物面積のすべてを一階に収めなければなりません。
建ぺい率50%の土地に建物面積30坪の平屋を建てる場合、最低限必要な土地面積は30坪÷50%=60坪という計算になります。
土地評価額は60坪×50万円/坪=3,000万円です。
今回は土地面積が60坪(198㎡)のため、200㎡以下の部分は小規模住宅用地の特例が適用されます。適用を受けた場合の土地の固定資産税は、以下のとおりです。
3,000万円×1/6×1.4%=7万円
次に建物の固定資産税を計算しましょう。
建物面積は30坪(99㎡)のため、新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置の適用対象です。
したがって建物の固定資産税は3年間1/2に減額されます。
減額後の固定資産税は以下のとおりです。
1,500万円×1.4%×1/2=10.5万円
最後に土地と建物の固定資産税を合算します。
7万円+10.5万円=17.5万円
30坪の新築二階建ての固定資産税シミュレーション
30坪の新築二階建ての固定資産税を以下の条件でシミュレーションします。
築年数:新築
構造:木造二階建て
建ぺい率:50%
容積率:100%
建物面積:30坪(99㎡)
土地面積:30坪(99㎡)
土地単価:50万円/坪
土地評価額:1,500万円
建物評価額:1,200万円
土地の固定資産税を計算しましょう。
二階建ての場合、平屋に比べて狭い土地でも建てられます。
一階の建物面積15坪+二階の建物面積15坪=30坪とした場合、最低限必要な土地面積は一階の建物面積を建ぺい率50%で割り戻して、15坪÷50%=30坪です。
したがって土地評価額は30坪×50万円/坪=1,500万円となります。
土地面積が30坪(99㎡)のため、200㎡以下の部分は小規模住宅用地の特例が適用されます。
適用を受けた場合の土地の固定資産税は以下のとおりです。
1,500万円×1/6×1.4%=3.5万円
さらに建物の固定資産税を計算します。
建物面積は30坪(99㎡)のため、新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置の適用対象です。
したがって建物の固定資産税は3年間1/2に減額されます。
減額後の固定資産税は以下のとおりです。
1,200万円×1.4%×1/2=8.4万円
最後に土地と建物の固定資産税を合算します。
3.5万円+8.4万円=11.9万円
平屋のほうが二階建てより固定資産税が高い
新築平屋と新築二階建てを比べると、新築平屋のほうが固定資産税が高い結果になりました。
平屋の固定資産税が高くなる理由は、主に二つ挙げられます。
まず、平屋は一階部分しかないため土地が広くなる分、土地の固定資産税が高くなります。
さらに平屋は屋根や基礎の量が多いため、建築コストも高いです。
使用する材料が多くなるほど建築コストは上がり、建物の固定資産税も上がります。
しかし今回のシミュレーションはあくまで一例を示したものです。
土地のエリアが異なる場合や、建物の仕様によっては異なる結果になる場合もあります。
購入を検討している新築平屋がある場合は、具体的な数値をあてはめて計算してみてください。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
新築平屋と中古平屋の固定資産税を比較

新築平屋と中古平屋の固定資産税を比較しましょう。
| 新築平屋 | 中古平屋 | |
|---|---|---|
| 土地の固定資産税 | 7万円 | 7万円 |
| 建物の固定資産税 | 10.5万円 | 13.02万円 |
| 土地+建物の固定資産税 | 17.5万円 | 20.02万円 |
30坪の中古平屋の固定資産税シミュレーション
30坪の中古平屋の固定資産税を以下の条件でシミュレーションします。
築年数:6年
構造:木造一階建て
建ぺい率:50%
容積率:100%
建物面積:30坪(99㎡)
土地面積:60坪(198㎡)
土地単価:50万円/坪
土地評価額:3,000万円
建物評価額:930万円
土地の固定資産税を計算します。
建ぺい率50%の土地に建物面積30坪の平屋が建っているため、土地面積は60坪とします。
土地評価額は60坪×50万円/坪=3,000万円です。
200㎡以下の部分は小規模住宅用地の特例が適用されるため、課税標準額が1/6に軽減されます。計算式は以下のとおりです。
3,000万円×1/6×1.4%=7万円
次に建物の固定資産税を計算しましょう。
建物評価額は築年数の経過とともに減少していると考えられるため、新築の建物評価額1,500万円に経過年数6年の経年減点補正率0.62を乗じて930万円としました。
築6年経過していると、新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置は受けられません。
建物評価額に税率をかけて固定資産税を計算します。
930万円×1.4%=13.02万円
最後に土地と建物の固定資産税を合算します。
7万円+13.02万円=20.02万円
新築平屋は建物の固定資産税の優遇を受けられる
今回のシミュレーションでは、新築平屋のほうが固定資産税が安い結果になりました。
しかしこれは一例に過ぎず、中古平屋の築年数や建物評価額によって結果は変わります。
建物は築年数が経過するにつれて、建物評価額が下がっていくのが一般的です。
そのため新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置を受けられなくても、中古平屋のほうが固定資産税が安くなることもあります。
ただし物価上昇などによって建物評価額が思うように下がらないケースもあるため注意が必要です。
また経年減点補正率の下限は0.2であるため、どれだけ築年数が古くても建物評価額がゼロになることはありません。
固定資産税を抑えられる平屋の特徴

固定資産税を抑えられる平屋には特徴があります。以下の特徴を持つ平屋を選ぶと、固定資産税を抑えやすいでしょう。
- 木造住宅
- 建築コストが安い
- 土地代が安い
- 長期優良住宅
- 完全分離型二世帯住宅
- ロフト・屋根裏
木造住宅
木造は鉄筋コンクリート造などに比べて、固定資産税を抑えやすいです。
2021年度の東京法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表を見ると、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の順に価格が上がっているのがわかります。
| 木造居宅 | 10.2万円/㎡ |
|---|---|
| 鉄骨造居宅 | 12.4万円/㎡ |
| 鉄筋コンクリート造居宅 | 15.8万円/㎡ |
参照元:令和3年度東京法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表
全国の建築物の着工状況をまとめた2022年度建築着工統計調査を見ても、木造の建築コストは鉄骨造、鉄筋コンクリート造に比べて安い結果です。
| 木造一戸建て | 18万円/㎡ |
|---|---|
| 鉄骨一戸建て | 30万円/㎡ |
| 鉄筋コンクリート造一戸建て | 33万円/㎡ |
参照元:2022年度建築着工統計調査・第34表
「木造は強度があるのか心配」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
木造でも耐震性や耐火性が高い建物は建てられます。
さらに平屋は構造的にも安定しているため、強度は十分です。
建築コストが安い
建築コストが安い平屋は、固定資産税も安くなります。
平屋の形状は正方形、長方形など凹凸が少ないほうが建築コストが安いです。
余計な装飾や住宅設備も減らして、シンプルに仕上げることがポイントです。
建物面積が広くなるほど建築コストは上がるため、無駄なスペースは省いてコンパクトに仕上げましょう。
また部屋数が多いほど、建築コストが上がる原因になります。
部屋の仕様によっても建築コストは異なり、洋室よりも和室のほうが高くなることが多いです。
土地代が安い
土地代が安いエリアを選ぶと、固定資産税の軽減につながります。
土地の固定資産税評価額は公示価格の7割程度です。
特に平屋は広い土地面積が必要になるため、土地代が固定資産税に与える影響は大きくなります。
都心や駅近の土地は利便性が高いですが、土地代も高額です。
近年はコロナショックの影響でリモートワークが定着し、毎日出社しない方も増えました。
そのような場合は、郊外のほうが土地の固定資産税を安く抑えられるでしょう。
長期優良住宅
長期優良住宅は新築から5年間、新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置を受けられるのがメリットです。
一般的な新築住宅よりも、2年延長されています。
期間限定の軽減措置ではありますが、建物にかかる固定資産税が1/2に減額される経済的なメリットは大きいといえるでしょう。
「長期優良住宅にすると建築コストが上がって固定資産税が高くなるのでは」と心配する方がいらっしゃるかもしれません。
しかし長期優良住宅だからといって、必ずしも高級な材料や設備を使っているわけではありません。
したがって長期優良住宅にしても固定資産税は高くならない可能性も十分あります。
完全分離型二世帯住宅
完全分離型二世帯住宅にすると、二世帯分に対して固定資産税の軽減措置を受けられます。
各世帯が独立的に区画されていて、それぞれが独立して生活できる状態が一般的な要件になります。
新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置は住宅1戸あたり床面積120㎡以下の部分が対象ですが、完全分離型二世帯住宅の場合は120㎡×2戸の240㎡以下の部分までが対象です。
住宅用地の課税標準の特例では、200㎡以下の部分の小規模住宅用地と200㎡超の部分の一般住宅用地に分けられています。
完全分離型二世帯住宅の場合は、400㎡以下の部分が小規模住宅用地、400㎡超の部分が一般住宅用地です。
ロフト・屋根裏
ロフトや屋根裏を設けると、固定資産税を抑えられる可能性があります。
建築基準法の条件を満たしている場合、ロフトや屋根裏の面積は固定資産税の課税対象面積に含まれません。
スペースを有効活用しつつ、固定資産税を抑えられるため一石二鳥です。
特に平屋は一階部分しかなくスペースが限られるため、ロフトや屋根裏を賢く活用することをおすすめします。
まとめ

建物面積30坪の平屋と二階建ての固定資産税は、平屋のほうが固定資産税が高くなりやすい傾向にあります。
平屋は広い土地が必要になるため土地の固定資産税が高くなることと、屋根や基礎の量が多くなり建物の固定資産税が高くなることが原因です。
建築コストや土地代が安い平屋を選ぶことで、平屋であっても固定資産税を抑えられる可能性があります。
ちゅうこだて!の「住まいの紹介サービス」では、中古一戸建て探しのご相談を24時間チャットで受け付けております。
ぜひお気軽にご利用ください。
\ 平屋の中古物件を探したい /
平屋の物件をお探しの方へ
ちゅうこだて!は中古一戸建ての物件情報を検索できるサイトです。
地域、駅・路線、相場、生活施設など、お好みの検索方法で物件の絞り込みができます。
平屋の固定資産税を抑えたい方は、新築平屋だけでなく中古平屋も視野に入れて物件を探してみてください。